
今日の板書はこれ!
\(a^2=b^2+c^2-2bc\cos{A}\)
\(b^2=c^2+a^2-2ca\cos{B}\)
\(c^2=a^2+b^2-2ab\cos{C}\)
(1) △ABCにおいて、\(b=\sqrt{3}\) 、\(c=2\)、\(A=150°\) のとき、\(a\) を求めよ。
(1) 余弦定理より
\(\color{red}{a^2}=\color{lime}{{(\sqrt{3}\:)}}^2+\color{lime}{{2\:}}^2\)
\(-2\cdot\color{lime}{\sqrt{3}}\cdot \color{lime}{2}\cdot\color{lime}{\cos{150°}}\)
\(=3+4-2\cdot\sqrt{3}\cdot 2\cdot\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right)\)
\(= 13\)
よって \(a>0\) より \(a=\sqrt{3}\)
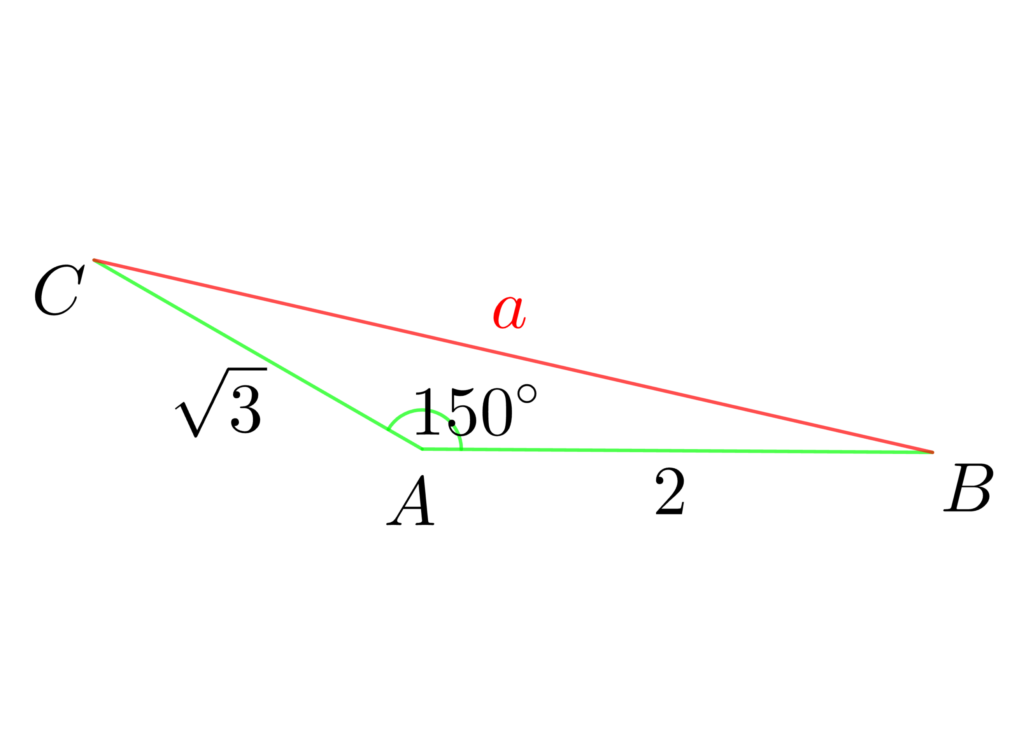
(2) △ABCにおいて、\(b=\sqrt{6}\) 、\(A=45°\)、\(B=60°\) のとき、\(a\) を求めよ。
(2) 余弦定理より
\(\displaystyle \cos{C}=\frac{\color{deepskyblue}{3}^2+\color{deepskyblue}{2}^2-(\color{deepskyblue}{\sqrt{7}})^2}{2\cdot \color{deepskyblue}{3}\cdot \color{deepskyblue}{2}}=\frac{1}{2}\)
よって
\(C = 60°\)
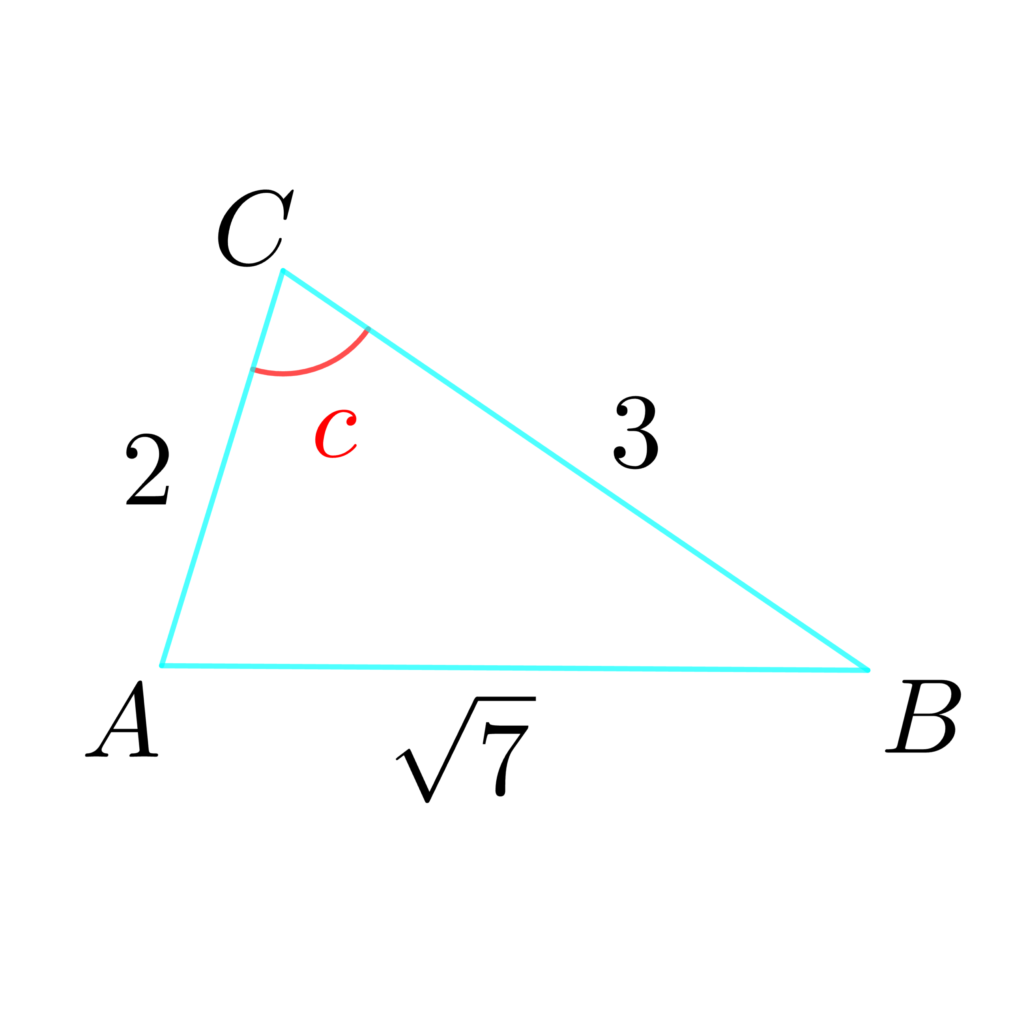

もっと詳しく願いします!!
「人より勉強に時間がかかる」と感じていませんか?
私の学校にも、同じ悩みを抱えて苦しんでる生徒がたくさんいます。
• 「教科書や参考書の内容がわからなくて、読むのに時間がかかる」
• 「解答の意味が理解できず、勉強が進まない」
教科書や参考書の内容を理解するには、「自分なりに噛み砕いて考える力」が必要です。
でも大丈夫!
このサイトでは、私が受けた質問や、つまずきポイントをもとに、わかりやすく解説していきます。
「噛み砕き方」がわかれば、文章はぐっと読みやすくなります!
余弦定理

正弦定理の次は余弦定理?

余弦はcosのことだよ!
\(a^2=b^2+c^2-2bc\cos{A}\)
\(b^2=c^2+a^2-2ca\cos{B}\)
\(c^2=a^2+b^2-2ab\cos{C}\)
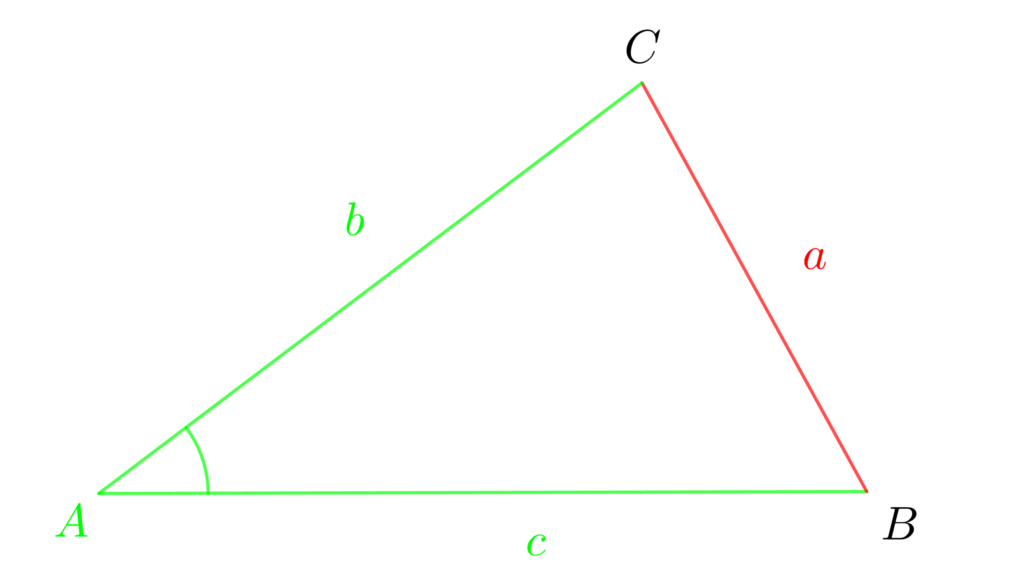
余弦定理は「隣り合う2辺とその間の角から対辺が分かる式」です。
この式をそのまま暗記するのではなく、図でイメージできるようにしておきましょう。
記事の後半で導出はしますが、余弦定理はもともと「三平方の定理」を使っています。
三平方の定理「\(a^2=b^2+c^2\)」に「\(-2bc\cos{A}\)」が加わったと考えれば、覚えやすいと思います。
余弦定理の使い方①

実際にはどうやって使うの?

余弦定理は「2辺とその間の角から対辺が分かる式」だったね。
このイメージを持っていると忘れにくくなり、どんな時に余弦定理を使えばいいかが分かるようになります。
次の例題で余弦定理を使ってみましょう。
△ABCにおいて、\(b=\sqrt{3}\) 、\(c=2\)、\(A=150°\) のとき、\(a\) を求めよ。
まずは、図を書いてみます。
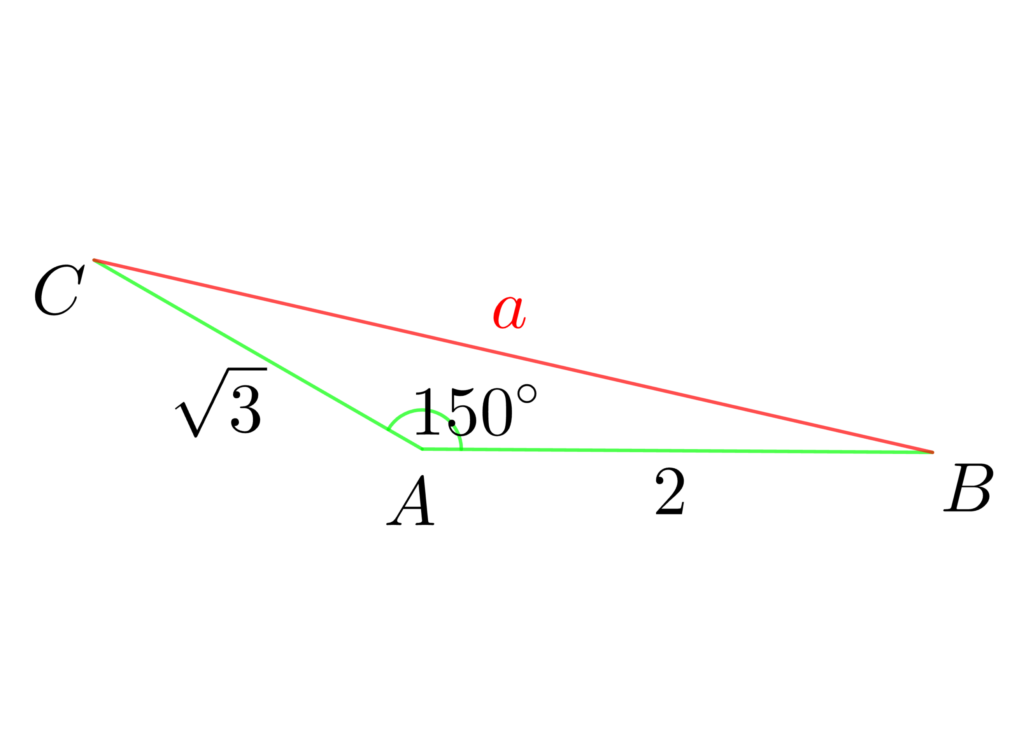
「2辺とその間の角から、対辺を求めるんだな」と認識できれば、あとは余弦定理を使いましょう。
よって \(a>0\) より \(a=\sqrt{3}\)
余弦定理の使い方②

次は、余弦定理を少し変形した式を使ってみよう!
余弦定理を「\(\cos =\)」の形に変形します。
\(\color{red}{a^2=b^2+c^2-2bc\cos{A}}\) より
\(2bc\cos{A}=b^2+c^2-a^2\)
よって \(\displaystyle\color{red}{\cos{A}=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} }\)
この式は、「3辺から角が分かる式」です。
式変形のイメージがあれば、暗記しようと頑張らなくても頭の中で導出することができます。
次の例題でこの式を使ってみましょう。
△ABCにおいて、\(b=\sqrt{6}\) 、\(A=45°\)、\(B=60°\) のとき、\(a\) を求めよ。
まずは、図を書いてみます。
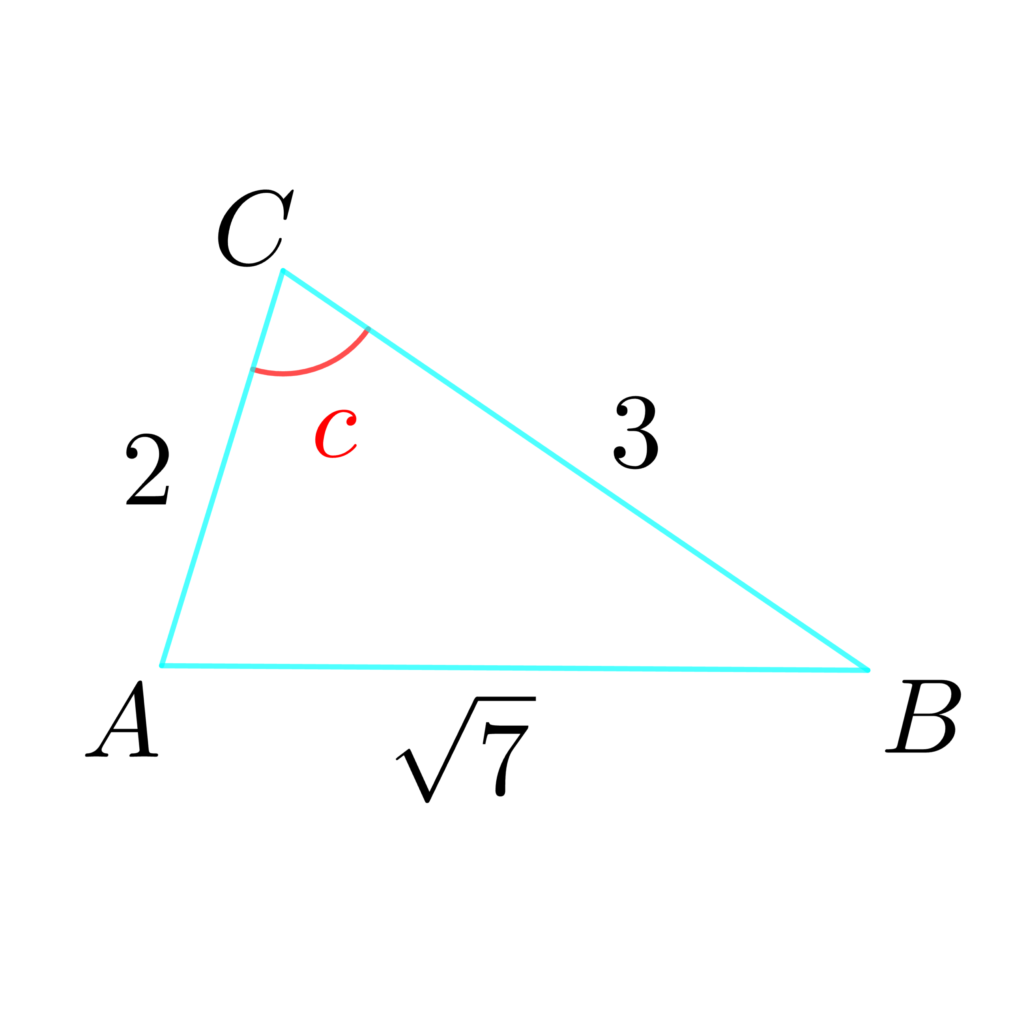
「3辺から、角を求めるんだな」と認識できれば、あとは余弦定理を使いましょう。
よって \(C = 60°\)
余弦定理が成り立つ理由

余弦定理はもともと三平方の定理ってどういうこと?

余弦定理を導出してみよう!
次の三角形で余弦定理 \(a^2=b^2+c^2-2bc\cos{A}\) を導出していきます。
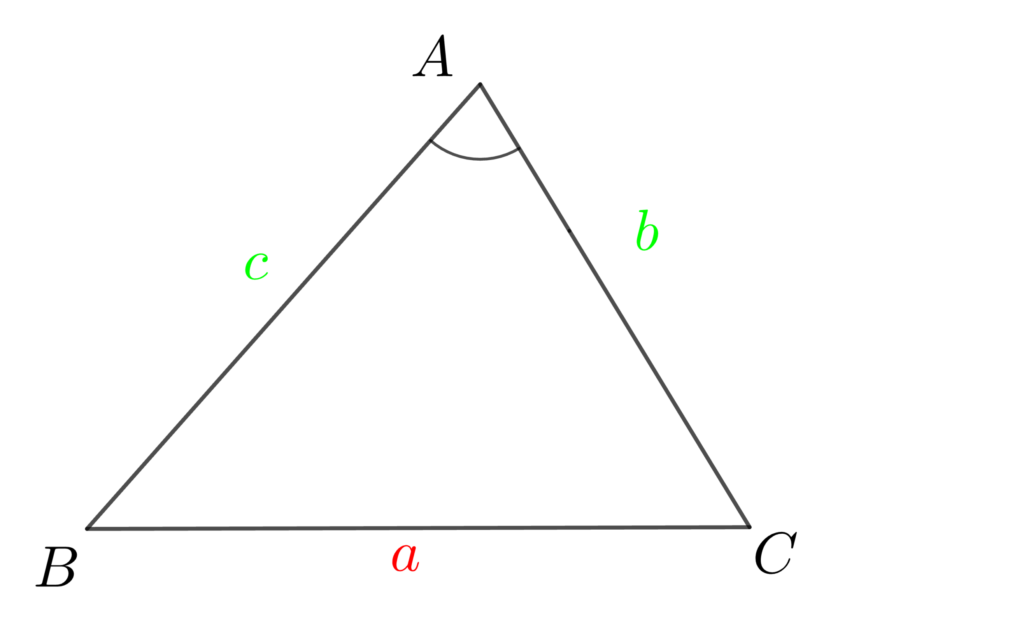
頂点BからACに垂線を引き、水色の直角三角形BCHで「三平方の定理」を使うと、それが「余弦定理」となります。
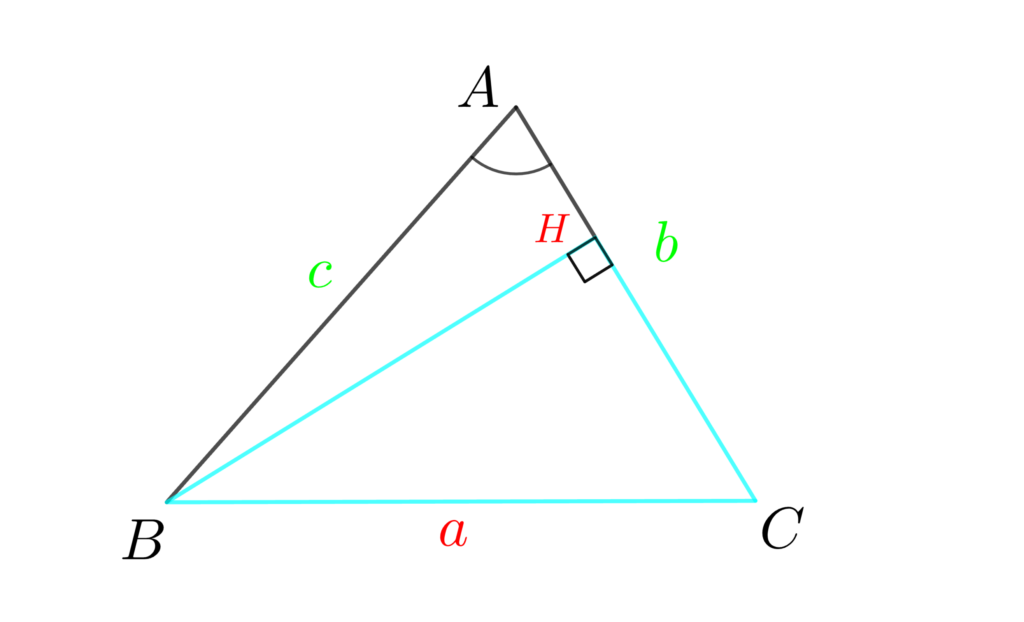
直角三角形BCHの1つの辺BCの長さは \(a\) と分かっていますので、残りの2辺BH、CHを求めていきます。
まずは、辺BHを考えます。直角三角形ABHより、\(BH=c\cdot\sin{A}\)
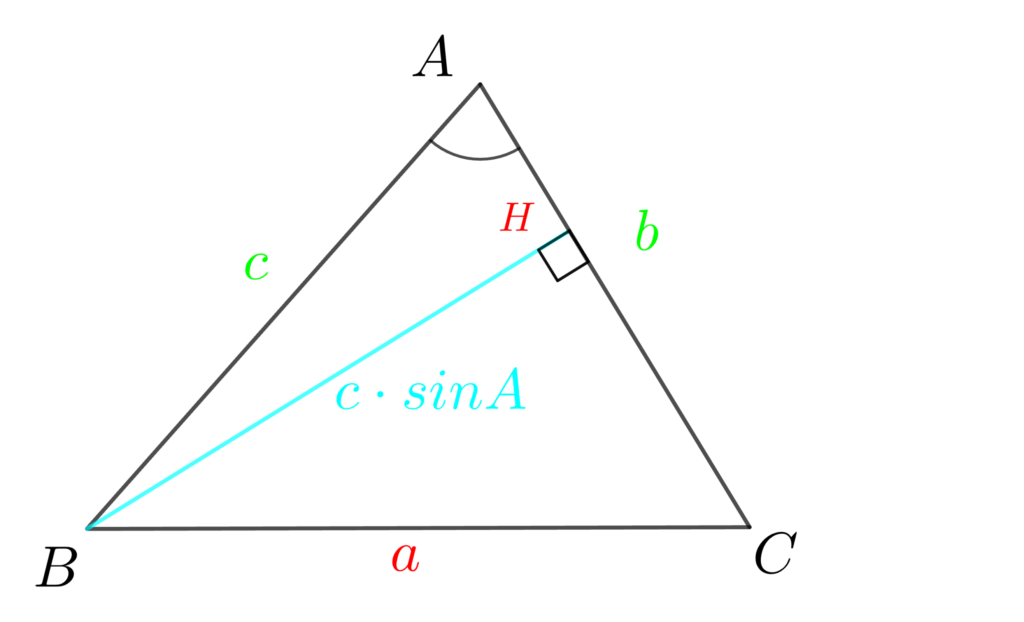
次に、辺CHを考えます。直角三角形ABHより、\(AH=c\cdot\cos{A}\) ですので、\(CH=b – c\cdot\cos{A}\)
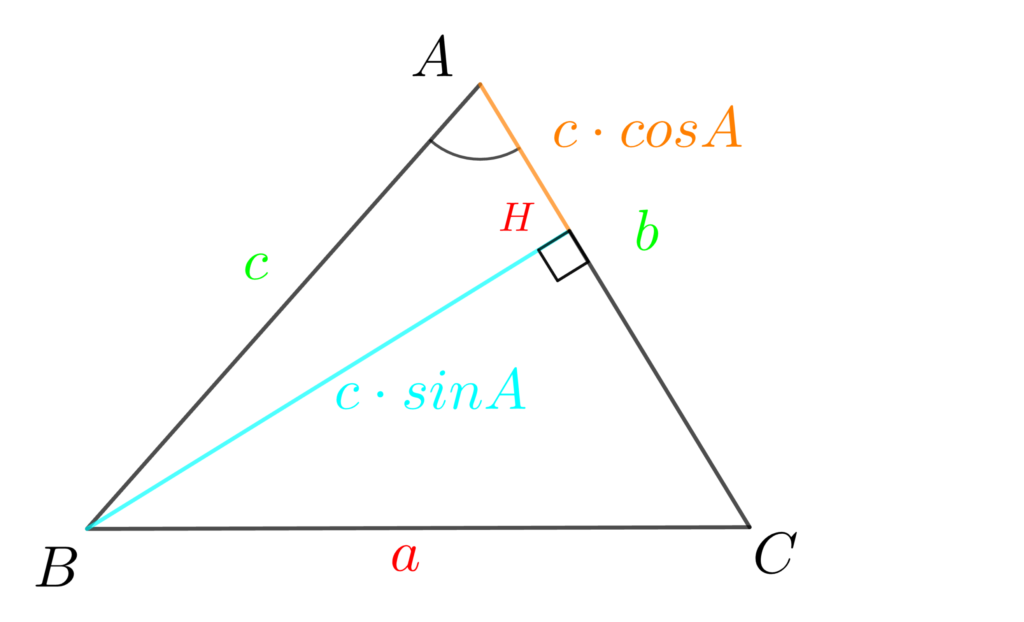
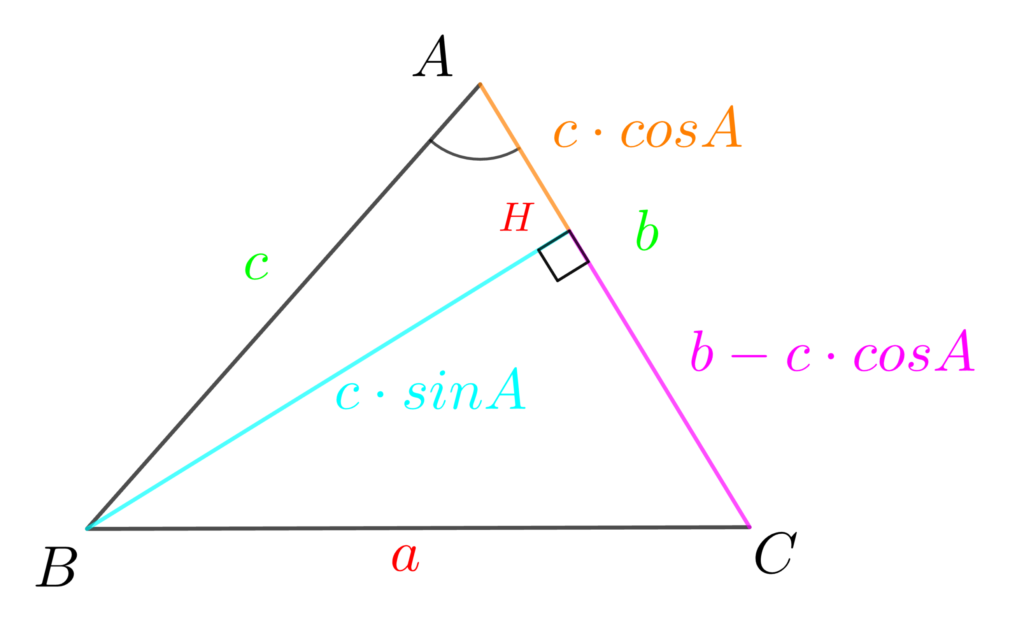
直角三角形BCHの3辺の長さが求まりましたので、あとは「三平方の定理」を使い「余弦定理」が導出します。

相互関係式 \({\sin{A}\:}^2+{\cos{A}}^2=1\) を使ったよ!覚えてるかな?
まとめ:余弦定理

さて、今回のまとめだよ!
余弦定理は「隣り合う2辺とその間の角から対辺が分かる式」であり、「3辺から角が分かる式」です。
\(a^2=b^2+c^2-2bc\cos{A}\)
\(b^2=c^2+a^2-2ca\cos{B}\)
\(c^2=a^2+b^2-2ab\cos{C}\)
(1) △ABCにおいて、\(b=\sqrt{3}\) 、\(c=2\)、\(A=150°\) のとき、\(a\) を求めよ。
(1) 余弦定理より
\(\color{red}{a^2}=\color{lime}{{(\sqrt{3}\:)}}^2+\color{lime}{{2\:}}^2\)
\(-2\cdot\color{lime}{\sqrt{3}}\cdot \color{lime}{2}\cdot\color{lime}{\cos{150°}}\)
\(=3+4-2\cdot\sqrt{3}\cdot 2\cdot\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right)\)
\(= 13\)
よって \(a>0\) より \(a=\sqrt{3}\)
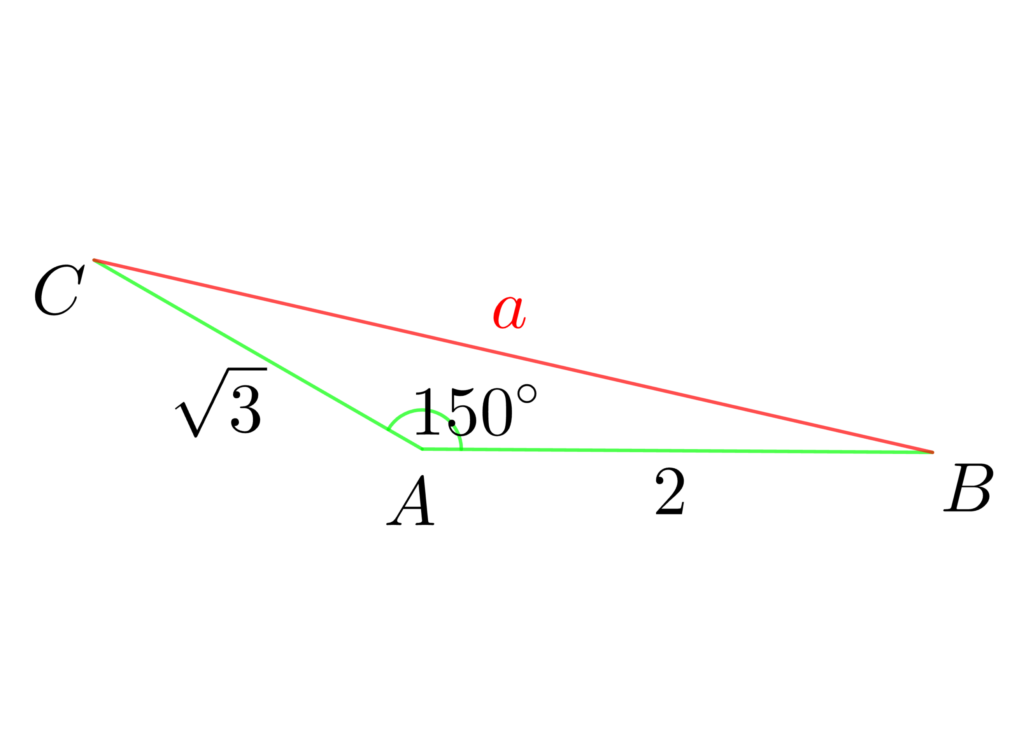
(2) △ABCにおいて、\(b=\sqrt{6}\) 、\(A=45°\)、\(B=60°\) のとき、\(a\) を求めよ。
(2) 余弦定理より
\(\displaystyle \cos{C}=\frac{\color{deepskyblue}{3}^2+\color{deepskyblue}{2}^2-(\color{deepskyblue}{\sqrt{7}})^2}{2\cdot \color{deepskyblue}{3}\cdot \color{deepskyblue}{2}}=\frac{1}{2}\)
よって
\(C = 60°\)
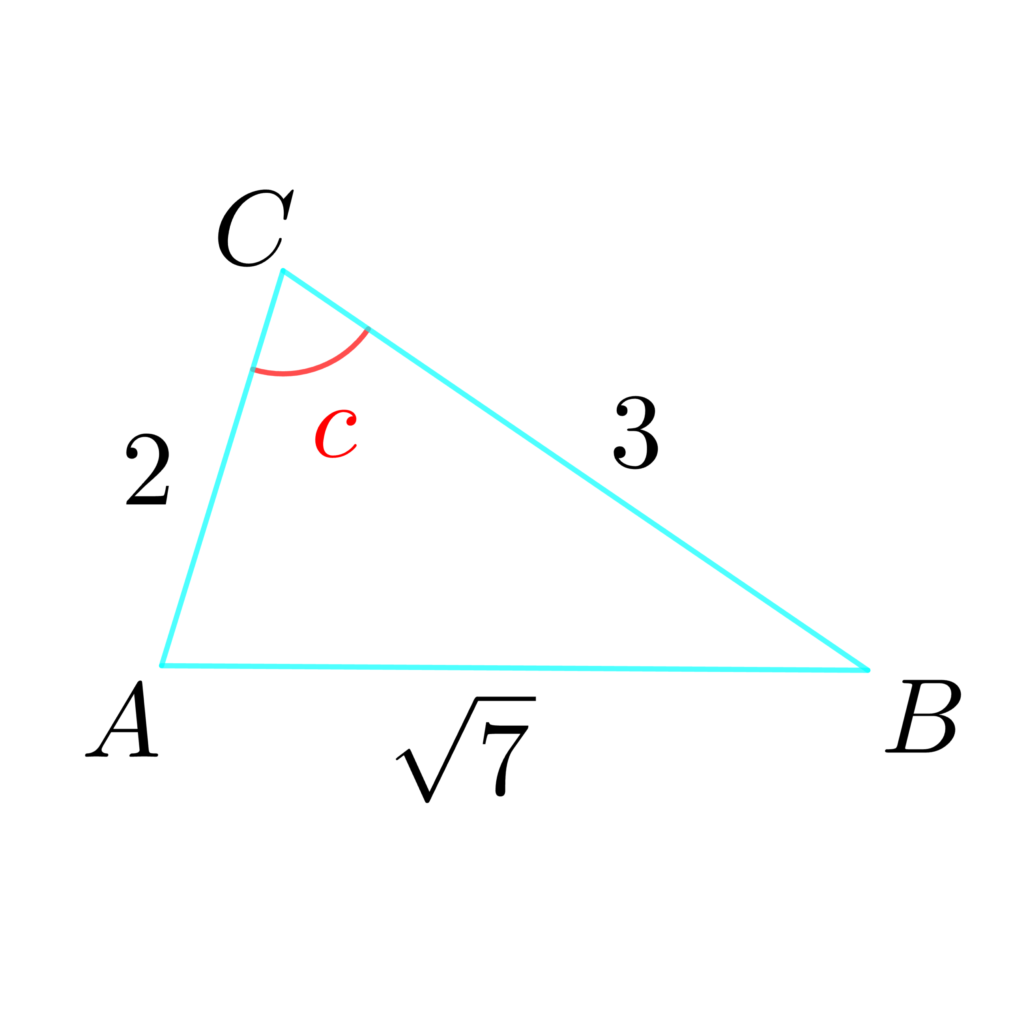

また一つ賢くなった!
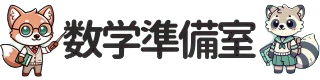
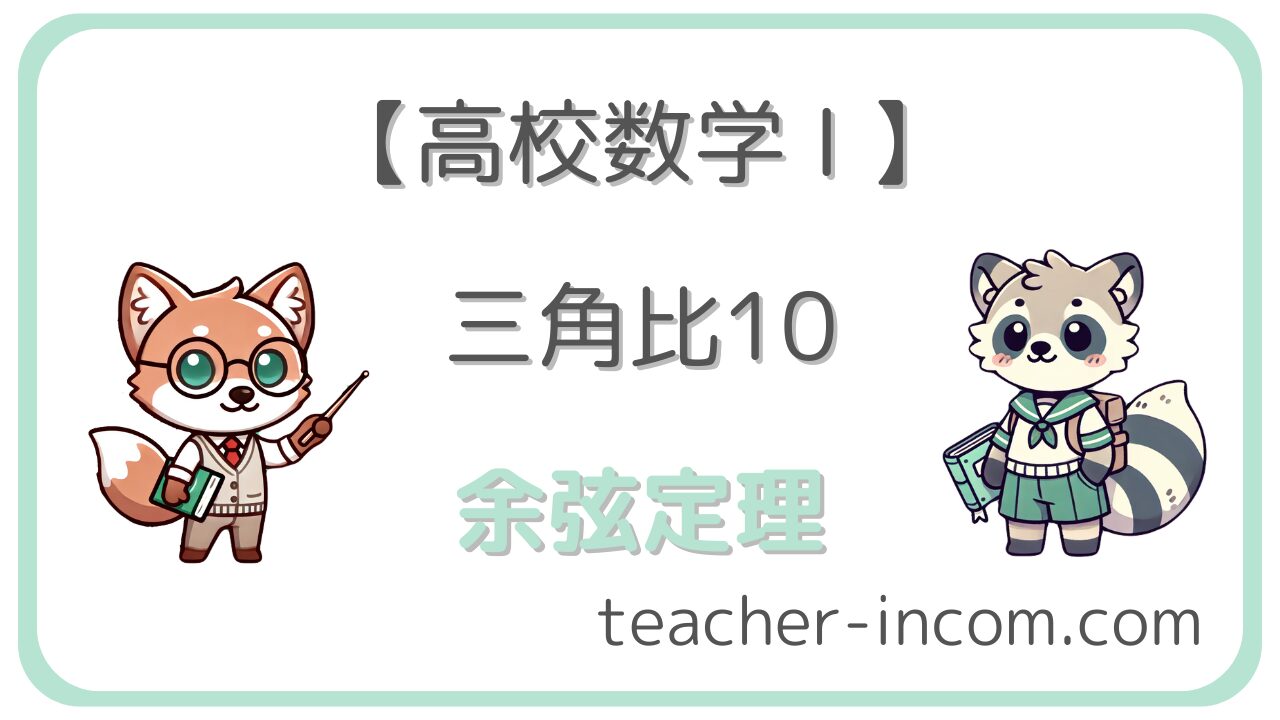
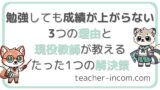
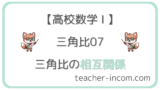
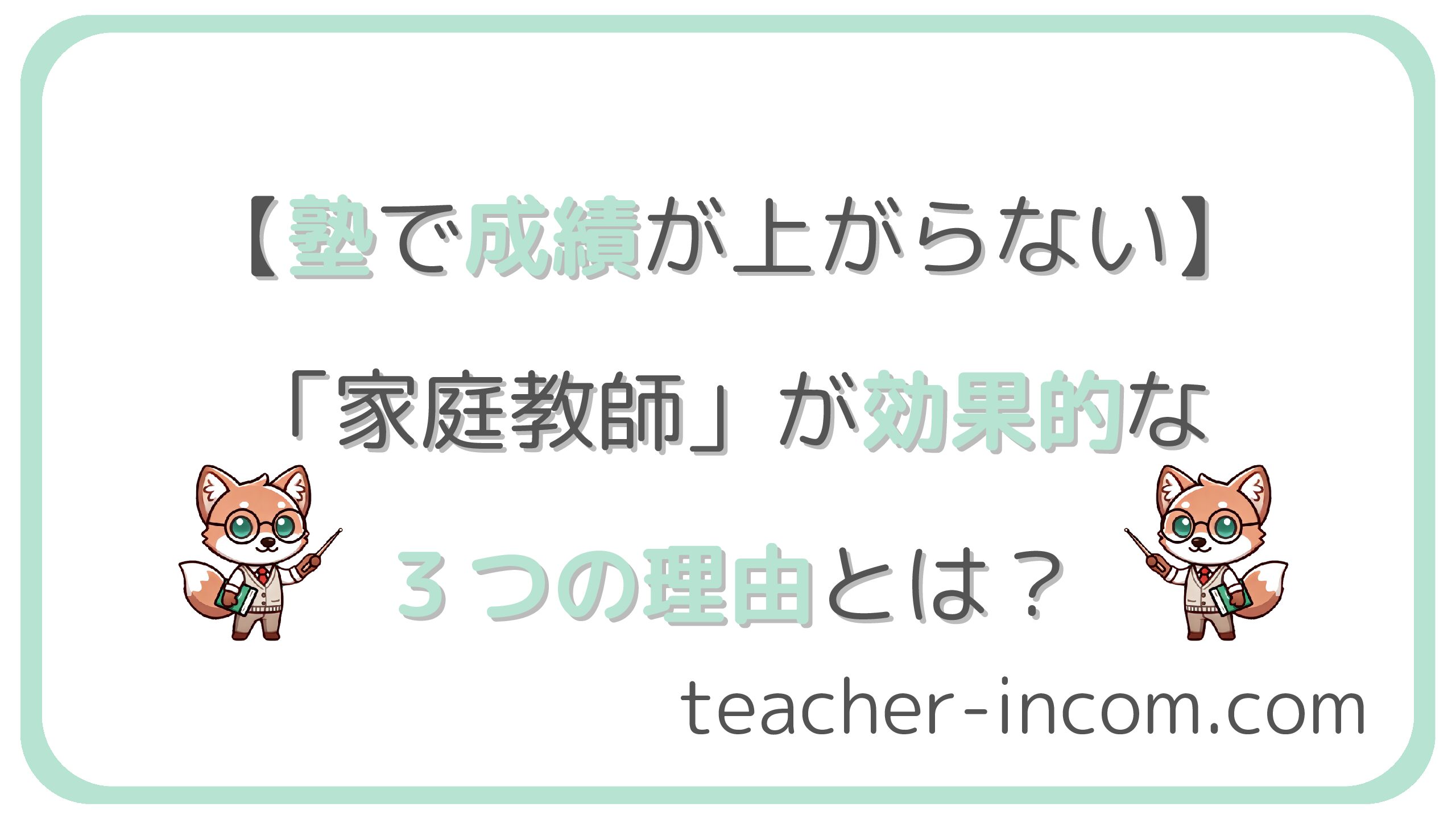
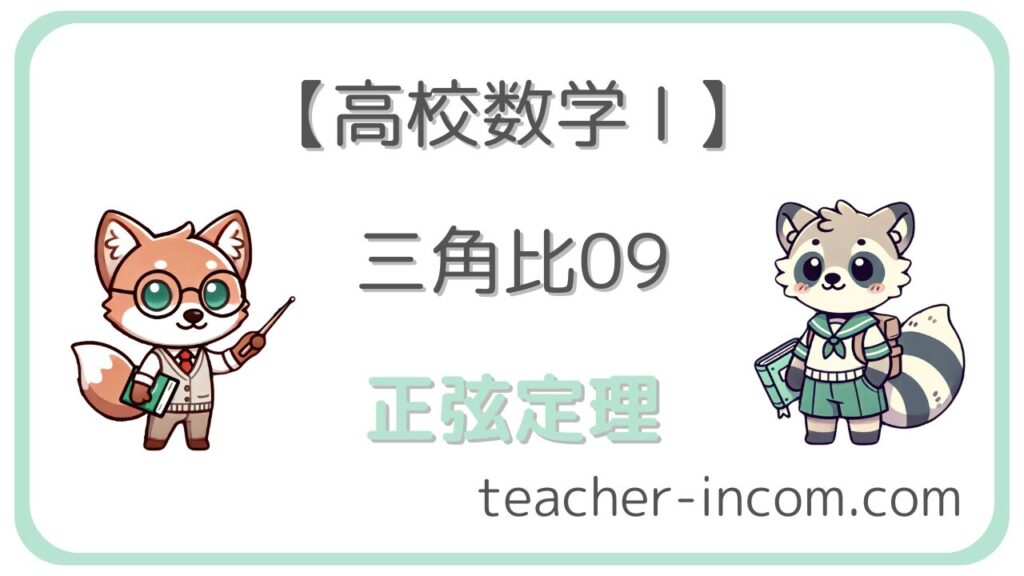
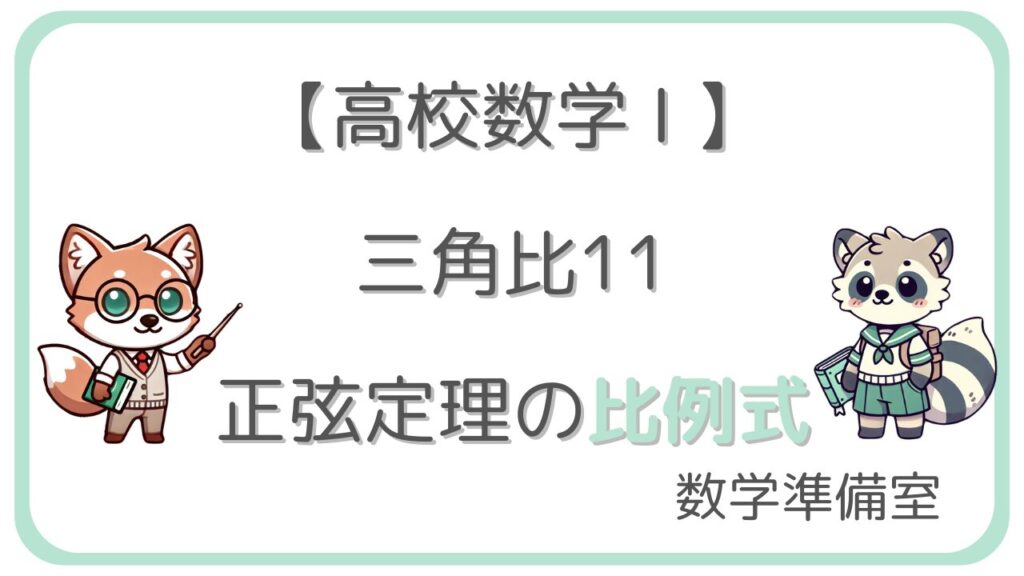
コメント