現役教員として数学を教えている「さん」と申します。
「人より勉強に時間がかかる」と感じていませんか?
私の学校にも、同じ悩みを抱えて苦しんでる生徒がたくさんいます。
• 「教科書や参考書の内容がわからなくて、読むのに時間がかかる」
• 「解答の意味が理解できず、勉強が進まない」
教科書や参考書の内容を理解するには、「自分なりに噛み砕いて考える力」が必要です。
でも大丈夫!
このサイトでは、私が受けた質問や、つまずきポイントをもとに、わかりやすく解説していきます。
意味から理解し、噛み砕き方をマスターしましょう!!
確率
確率01:確率の定義
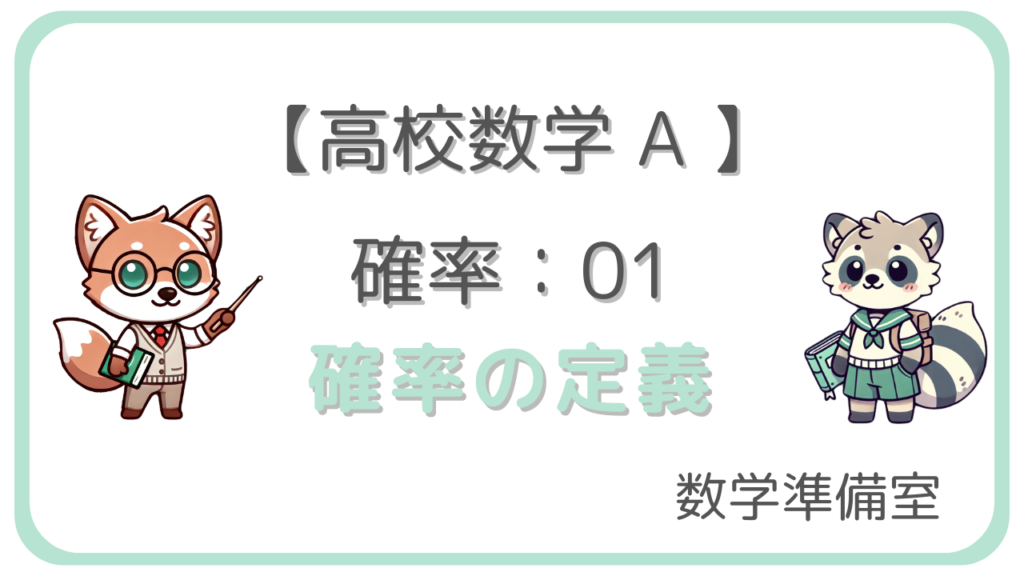
試行
…同じ条件で繰り返すことができ、結果が偶然によて確定する行為。
事象
…試行の結果として起こる事柄。AやBで表す。
根元事象
…それ以上分割することができない事象
全事象
…根元事象全体からなら事象。Uで表す。
空事象
…全く怒らない事象。∅で表す。
確率
…着目する事象の起こりやすさを全事象に対する割合として数値化したもの。全事象Uのどの根元事象も同様に確からしい(同程度起こりやすい)とき事象Aの確率は
\(\displaystyle P(A)=\frac{n(A)}{n(U)}=\frac{(事象Aが起こる場合の数)}{(起こりうる全ての場合の数)}\)
※確率は同じモノでも区別して考える。
確率02:確率を求める手順
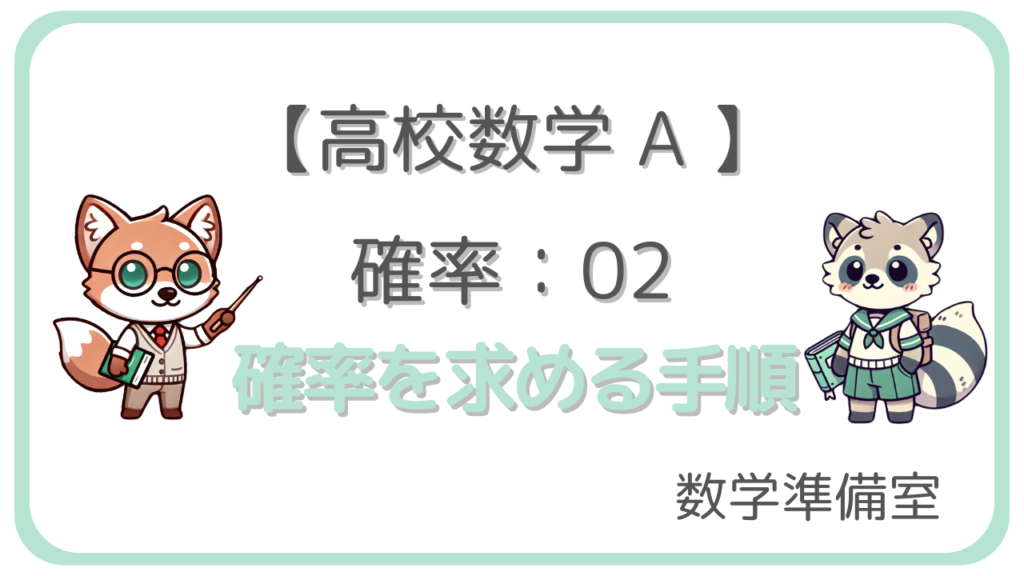
[1] 全事象を何にするかを自分で決める。根元事象が同様に確からしいならば、全事象の取り方は自由である。
[2] 全事象の要素数(分母)を求め、同基準で事象Aの要素数(分子)を求める。
確率03:確率の加法定理
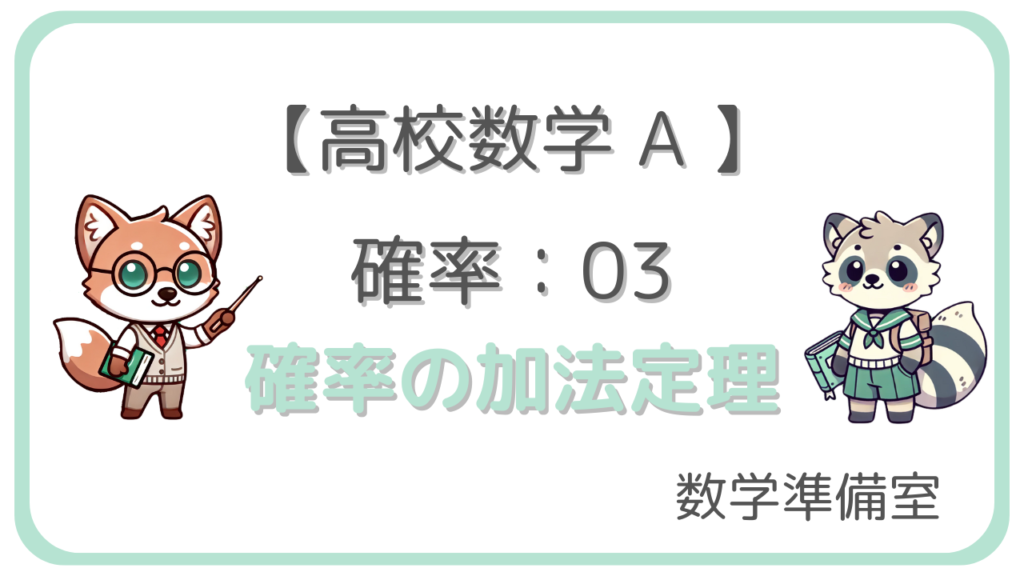
事象A,Bが同時にはおこらないとき、つまり\(A\cap B=\emptyset\)のとき、事象A,Bは互いに排反であるという。
事象A,Bが互いに排反であるとき、確率の加法定理が成り立つ
\(P(A\cap B)=P(A)+P(B)\)
(AまたはBの確率)=(Aの確率)+(Bの確率)
確率04:余事象の確率
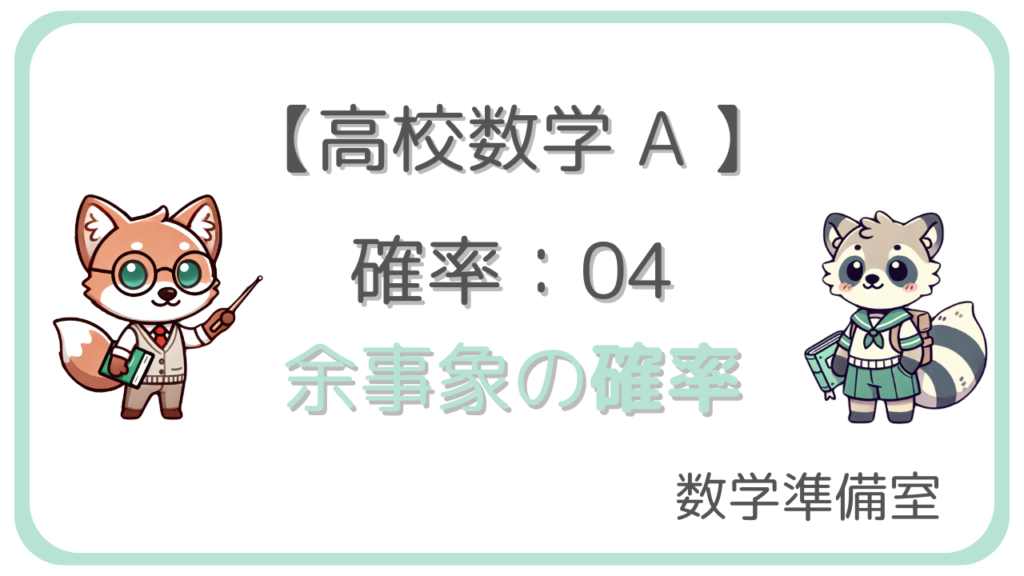
事象Aに対し、Aが起こらない事象をAの余事象といい、\(\overline{A}\)と表す。
このとき、全事象Uの確率は\(P(U)=P(A)+P(\overline{A})=1\)である。
この式から、\(P(A)\)と\(P(\overline{A})\)のどちらかがわかれば、もう一方も求められる。(つまり、\(P(\overline{A})=1-P(A)\))
特に「〜でない」「少なくとも〜」といった表現が出てきたら、余事象を使うとスムーズに解けることが多い。
確率05:独立試行の確率
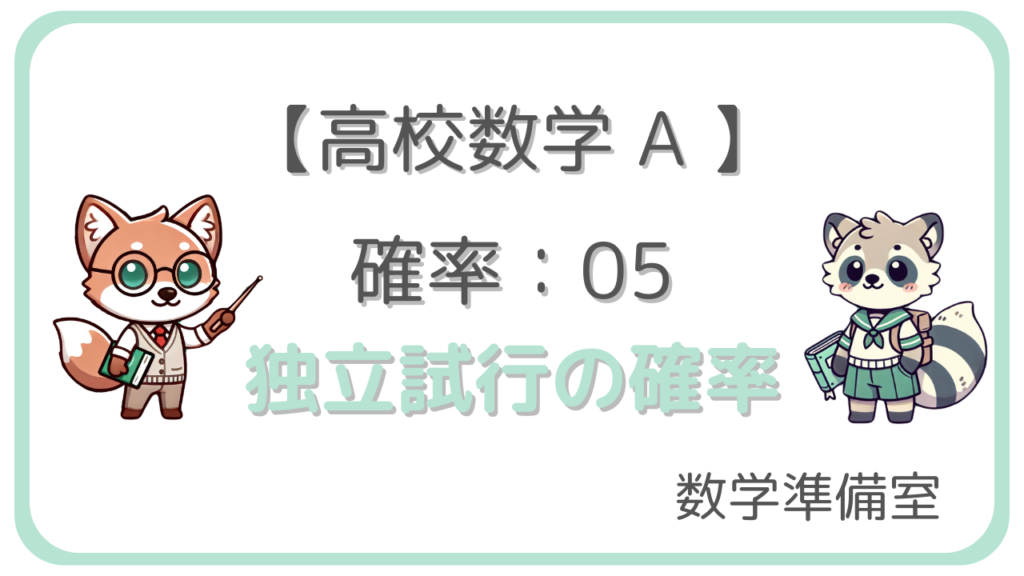
2つの試行S,Tにおいて、一方の試行の結果がもう一方の試行に影響を与えないとき、試行S,Tは独立であるという。
試行Sで事象Aが起こり、試行Tで事象Bが起こるとき、独立である場合には次の関係が成り立つ。
\(P(A\cap B)=P(A)P(B)\)
確率06:反復試行の確率
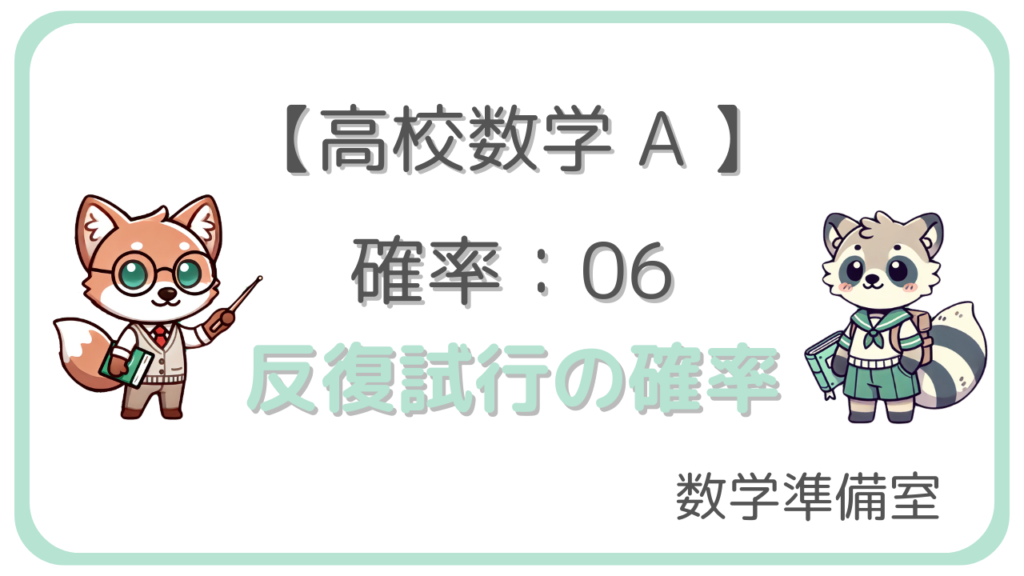
同じ条件で同じ試行を繰り返すとき、各回の試行は互いに独立である。このような独立な試行を何度も行うことを反復試行という。
試行を \(n\) 回繰り返すとき、事象Aが \(r\) 回起こる確率は、\(_nC_rp^n(1-p)^{n-r}\)で表される。
確率07:反復試行による直線上の点の移動
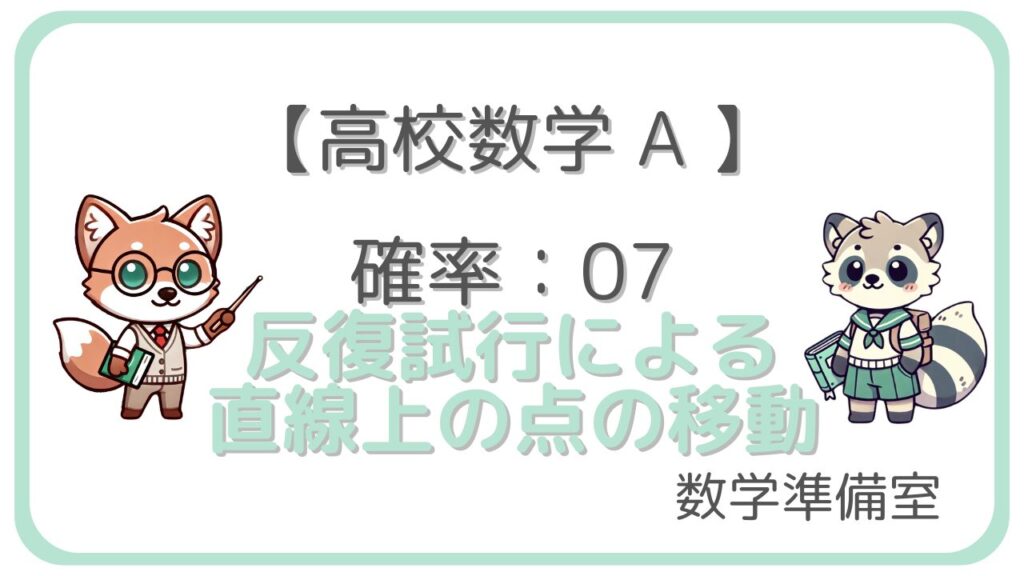
「どの事象が何回起これば目的の状態になるか」を考え、その回数に対応する反復試行の確率を求める。
確率08:条件付き確率
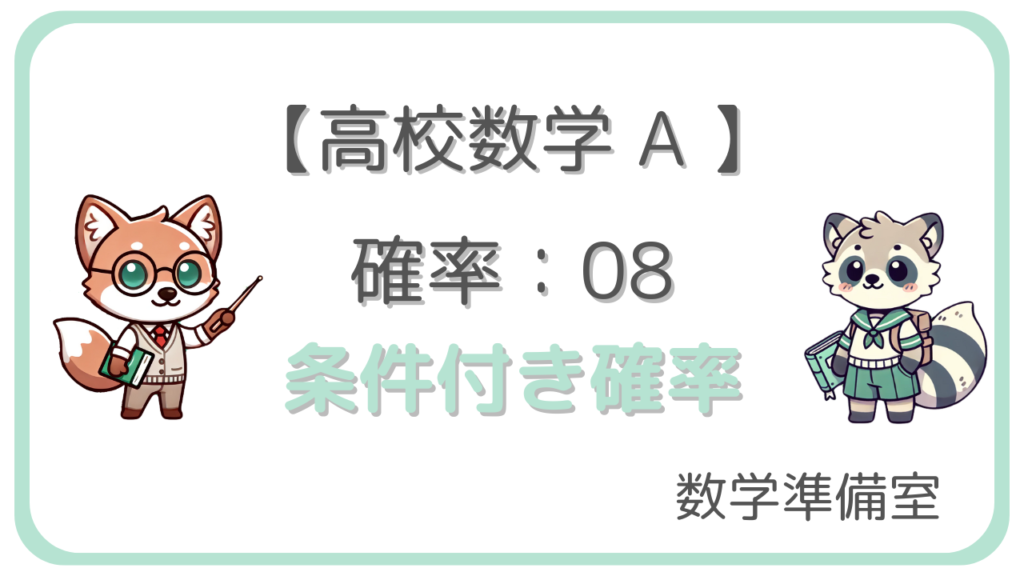
事象Aが起こったときに事象Bが起こる確率(条件付き確率)を\(P_A(B)\)で表す。
\(n(A)≠0,\:P(A)≠0\)のとき\(\displaystyle P_A(B)=\frac{n(A\cap B)}{n(A)}=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}\)
確率09:確率の乗法定理
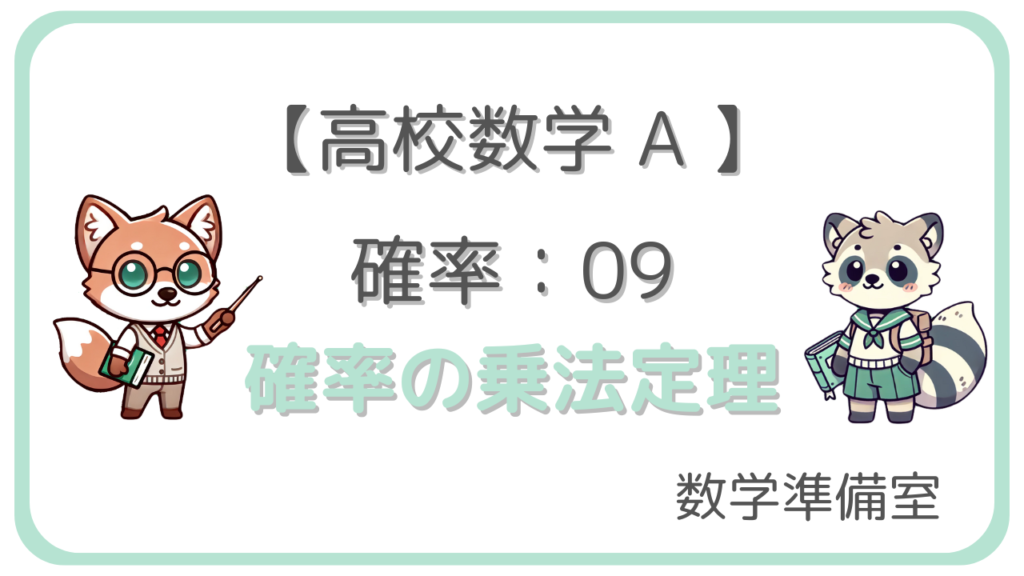
\(P(A\cap B)=P(A)P_A(B)\)
確率10:期待値
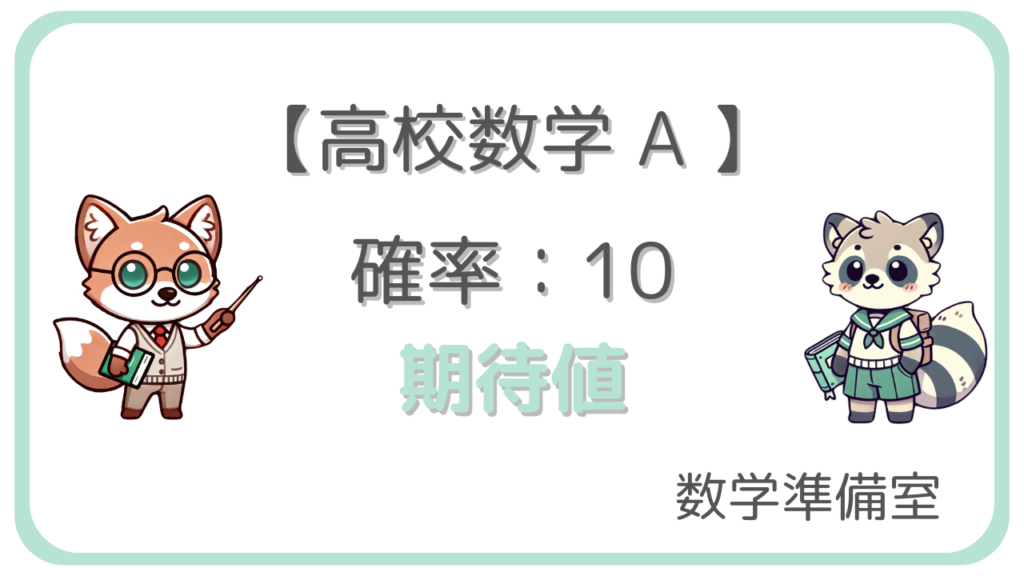
変数Xは、\(x_1,x_2,\cdots,x_n\) のうちどれか1つの値をとる。
また、その値をとる確率がそれぞれ\(P_1,P_2,\cdots,P_n\)である。(\(P_1+P_2+\cdots +P_n=1\))
このとき、\(E(x)=x_1P_1+x_2P_2+\cdots+x_nP_n\)を変数Xの期待値という。
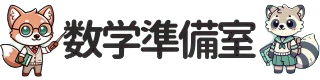
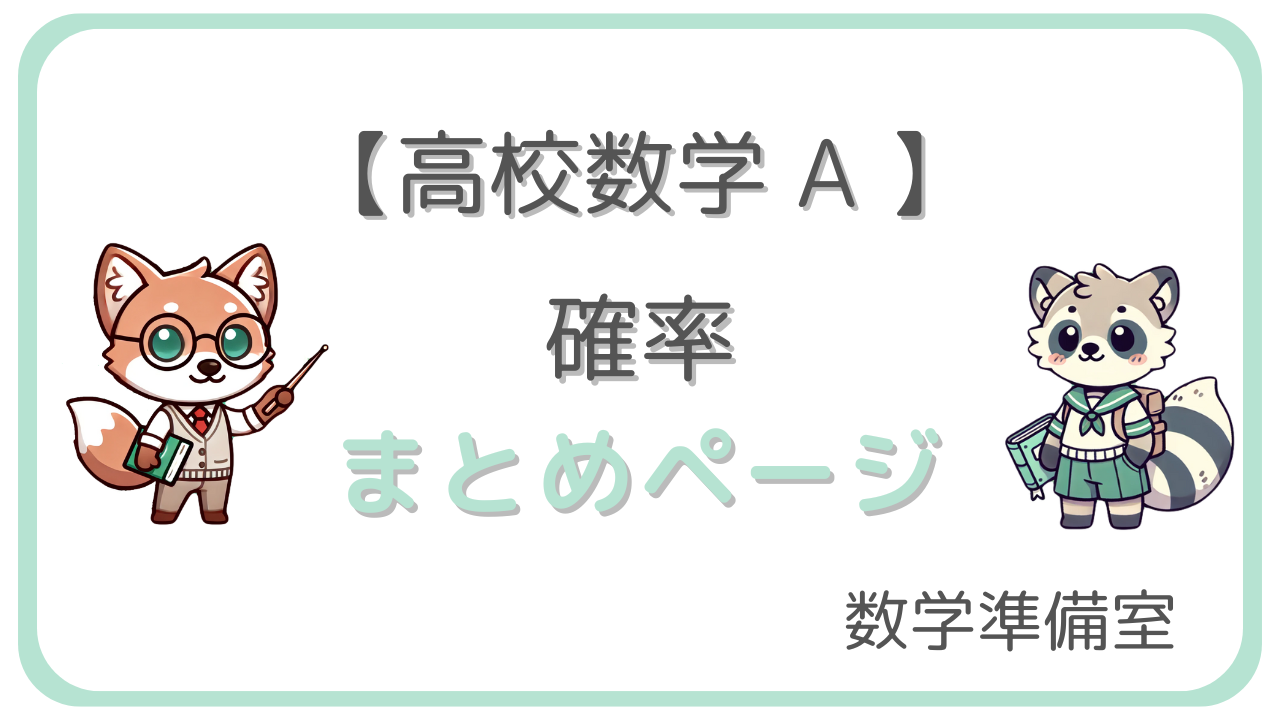
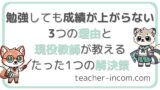

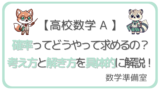
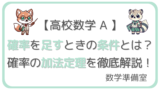
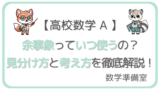
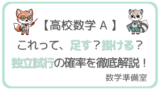
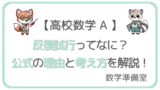
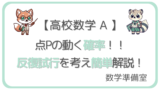


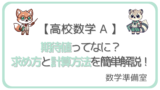
コメント