
今日の板書はこれ!
事象Aに対し、Aが起こらない事象をAの余事象といい、\(\overline{A}\)と表す。
このとき、全事象Uの確率は\(P(U)=P(A)+P(\overline{A})=1\)である。
この式から、\(P(A)\)と\(P(\overline{A})\)のどちらかがわかれば、もう一方も求められる。(つまり、\(P(\overline{A})=1-P(A)\))
特に「〜でない」「少なくとも〜」といった表現が出てきたら、余事象を使うとスムーズに解けることが多い。

もっと詳しく願いします!!
現役教員として数学を教えている「さん」と申します。
「人より勉強に時間がかかる」と感じていませんか?
私の学校にも、同じ悩みを抱えて苦しんでる生徒がたくさんいます。
• 「教科書や参考書の内容がわからなくて、読むのに時間がかかる」
• 「解答の意味が理解できず、勉強が進まない」
教科書や参考書の内容を理解するには、「自分なりに噛み砕いて考える力」が必要です。
でも大丈夫!
このサイトでは、私が受けた質問や、つまずきポイントをもとに、わかりやすく解説していきます。
意味から理解し、噛み砕き方をマスターしましょう!!
余事象の確率

次の問題を考えよう!
(1) 1から100までの番号札から1枚引くとき、5の倍数でない番号を引く確率を求めよ。
(2) 1から9までの番号札9枚から4枚を同時にひくとき、少なくとも1枚が偶数の番号である確率を求めよ。
(1)では「5の倍数でない確率」、(2)では「少なくとも1枚が偶数である確率」を求めます。
どちらも直接求めにくいタイプの問題ですね。
こうした場合は、それ以外の事象(=余事象)を考えるのがポイントです。
「~でない」や「少なくとも~」という表現が出てきたときは、
「じゃあ反対の事象を考えて、そこから1を引こう」と考えるとスムーズです。
つまり、「余事象の確率」を求めて、全体の1(=全事象の確率)から引くことで、間接的に求めることができます。

直接求めにくいときは、1から余事象の確率を引けばいいんだね!
「~でない」の確率
(1) 1から100までの番号札から1枚引くとき、5の倍数でない番号を引く確率を求めよ。
「5の倍数でない」確率を求めたいときは、その反対の事象(=余事象)である「5の倍数を引く」確率を考えます。
全事象は「100枚から1枚を引く」ので、\(100\)通り。
余事象は「5の倍数を引く」場合で、\(100÷5=25\)通り。
したがって、余事象の確率は、\(\displaystyle \frac{25}{100}=\frac{1}{4}\)
求めたい確率(=5の倍数でない確率)は、全体の確率1から余事象の確率を引いて求めます。
\(\displaystyle 1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}\)
「少なくとも~」の確率
(2) 1から9までの番号札9枚から4枚を同時にひくとき、少なくとも1枚が偶数の番号である確率を求めよ。
「少なくとも1枚が偶数を引く確率」を求めたいときは、その反対の事象(=余事象)である「すべて奇数を引く」確率を考えます。
「少なくとも~」はその余事象「すべて~」を考えます。
事象は「9枚から4枚を引く」場合なので、\(_9C_4\)通り。
一方、余事象「すべて奇数を引く」場合は、奇数が5枚あるので、」\(_5C_4\)通り。
したがって、余事象の確率は、\(\displaystyle \frac{_5C_4}{_9C_4}=\frac{5}{126}\)
求める確率(少なくとも1枚は偶数)は、全体の1から余事象を引いて求めます。
\(\displaystyle 1-\frac{5}{126}=\frac{121}{126}\)

「少なくとも〜」の問題では、反対の「すべて〜」を考えるのがコツだよ。
まとめ:余事象の確率

さて、今回のまとめだよ!
事象Aに対し、Aが起こらない事象をAの余事象といい、\(\overline{A}\)と表す。
このとき、全事象Uの確率は\(P(U)=P(A)+P(\overline{A})=1\)である。
この式から、\(P(A)\)と\(P(\overline{A})\)のどちらかがわかれば、もう一方も求められる。(つまり、\(P(\overline{A})=1-P(A)\))
特に「〜でない」「少なくとも〜」といった表現が出てきたら、余事象を使うとスムーズに解けることが多い。

ありがとうございました!!
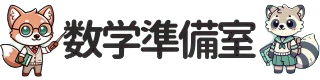
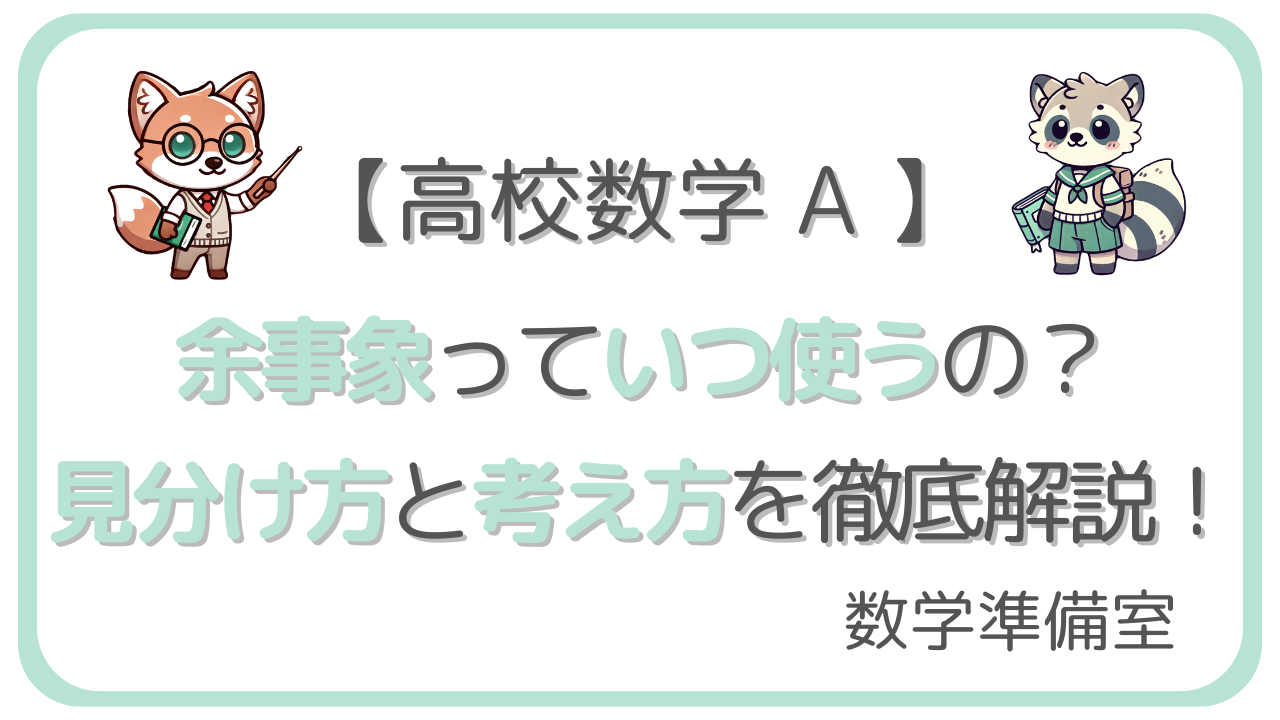
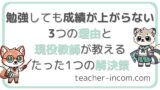
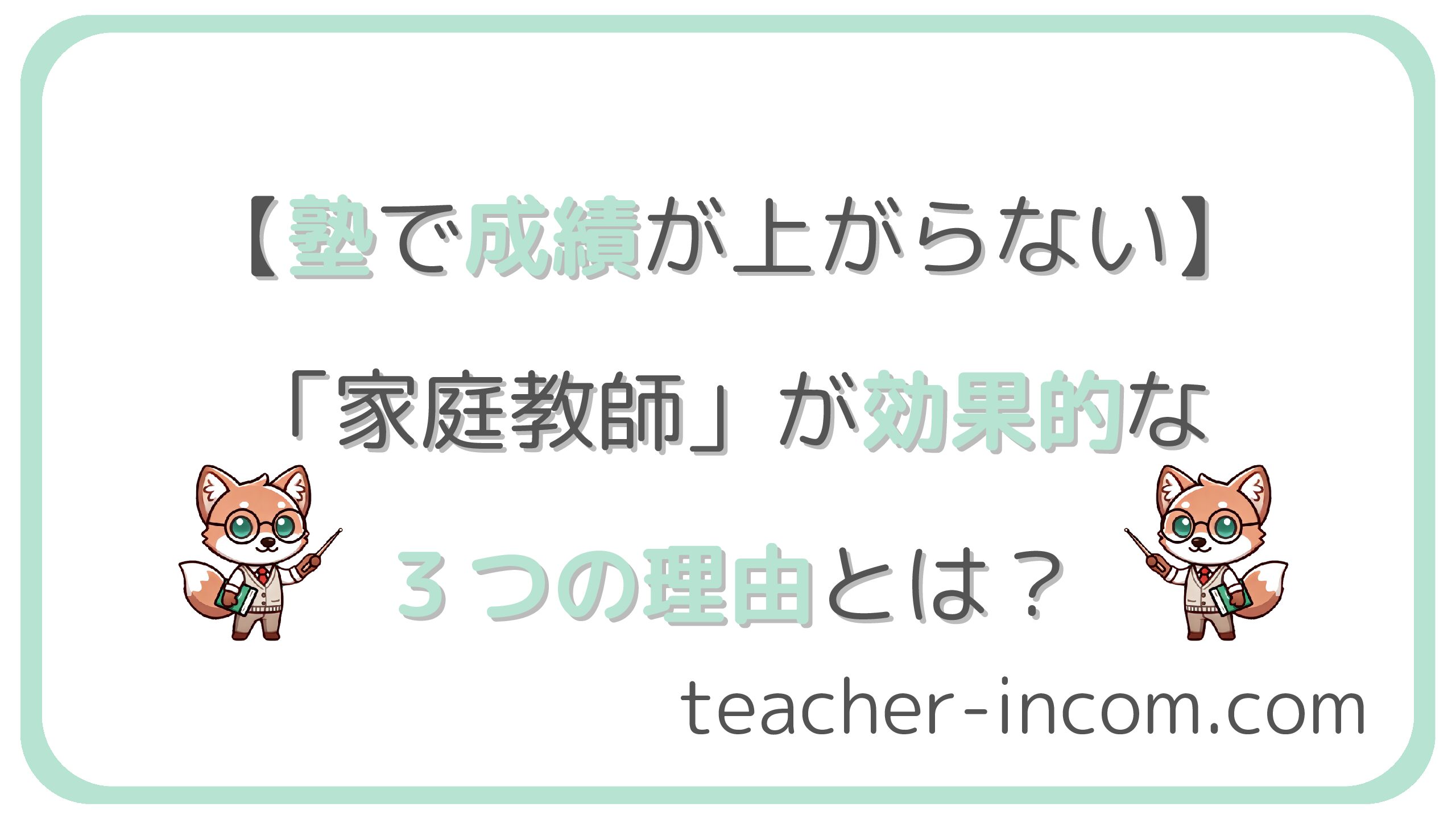
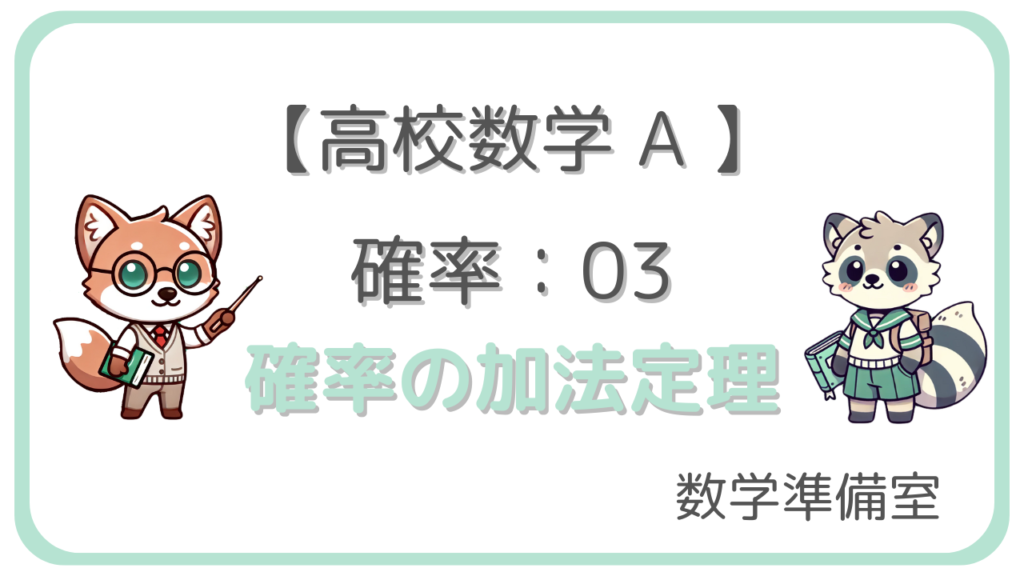
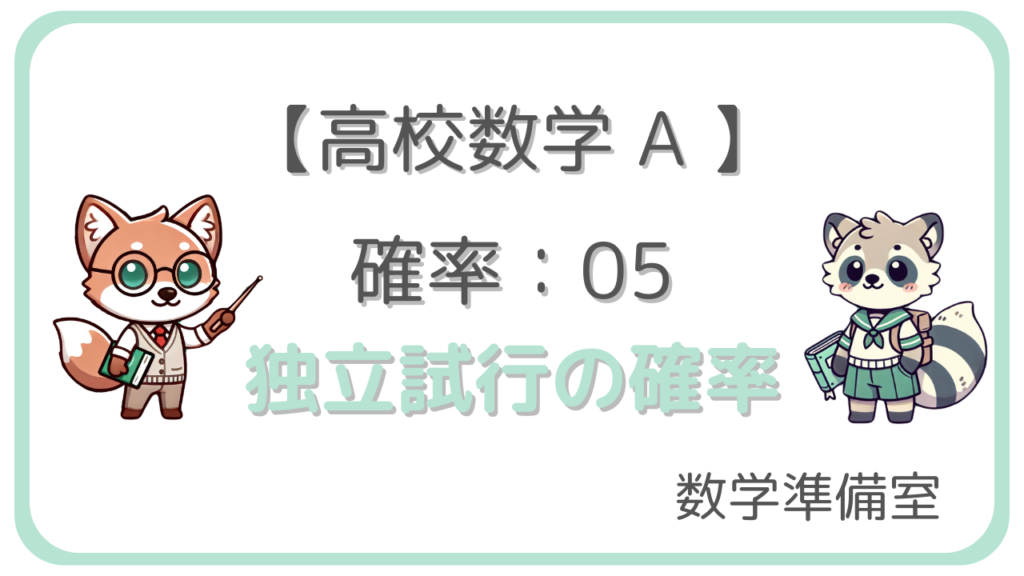
コメント