
今日の板書はこれ!
2つの試行S,Tにおいて、一方の試行の結果がもう一方の試行に影響を与えないとき、試行S,Tは独立であるという。
試行Sで事象Aが起こり、試行Tで事象Bが起こるとき、独立である場合には次の関係が成り立つ。
\(P(A\cap B)=P(A)P(B)\)

もっと詳しく願いします!!
現役教員として数学を教えている「さん」と申します。
「人より勉強に時間がかかる」と感じていませんか?
私の学校にも、同じ悩みを抱えて苦しんでる生徒がたくさんいます。
• 「教科書や参考書の内容がわからなくて、読むのに時間がかかる」
• 「解答の意味が理解できず、勉強が進まない」
教科書や参考書の内容を理解するには、「自分なりに噛み砕いて考える力」が必要です。
でも大丈夫!
このサイトでは、私が受けた質問や、つまずきポイントをもとに、わかりやすく解説していきます。
意味から理解し、噛み砕き方をマスターしましょう!!
独立試行の確率
今回は「事象Aかつ事象Bが起こる確率」を求めていきます。
「AかつB」が起こる確率は、それぞれの確率を掛け合わせることで求めることができます。
一方、「AまたはB」が起こる確率は、それぞれの確率を足すことで求めました(確率の加法定理)。
この「足す」と「掛ける」を混同してしまう生徒がとても多いです。
そこで今回は、どんなときに足し算・掛け算を使うのかを、例題を通してしっかり理解していきましょう。

次の例題で考えよう!
例題
Aの袋には赤玉3個と白玉2個、Bの袋には赤玉2個と白玉4個が入っている。A,Bの袋から1個ずつ玉を取り出すとき、同じ色の玉を取り出す確率を求めよ。
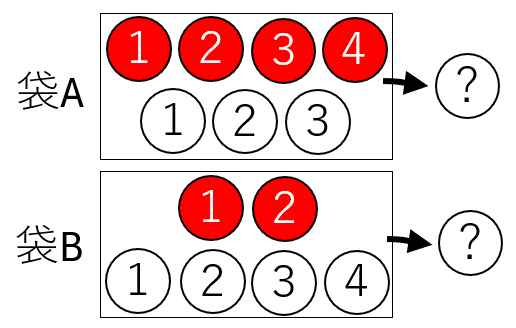
Step 1:事象を分けて考える
「A・Bの袋から同じ色の玉を取り出す」事象は、次の2つに分けられます。
- 両方とも赤を取り出す
- 両方とも白を取り出す
それぞれの確率を順に求めていきましょう。
Step 2:「両方とも赤を取り出す確率」
まずは、「両方とも赤を取り出す確率」を求めます。
Aの袋から赤玉を取り出す確率は、\(\displaystyle \frac{3}{5}\)
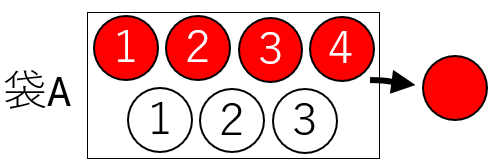
Bの袋から赤玉を取り出す確率は、\(\displaystyle \frac{2}{6}\)
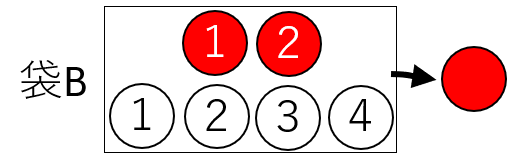

これらの確率って、掛ける?それとも足す?

え…。どっちだろ?
正解は、「掛ける」です。
「両方とも赤を取り出す確率」は、「Aの袋から赤玉を取り出す」かつ「Bの袋から赤玉を取り出す」こと。
このように、両方の事象が同時に起こらなければならないときは、確率を掛けて求めます。
よって、「両方とも赤を取り出す確率」は、\(\displaystyle \frac{3}{5}×\frac{2}{6}\)
Step 3:「両方とも白を取り出す確率」
Aの袋から白玉を取り出す確率は、\(\displaystyle \frac{2}{5}\)
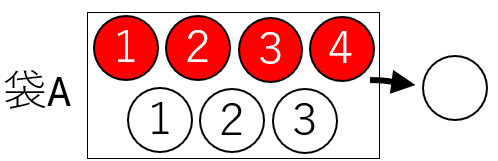
Bの袋から白玉を取り出す確率は、\(\displaystyle \frac{4}{6}\)
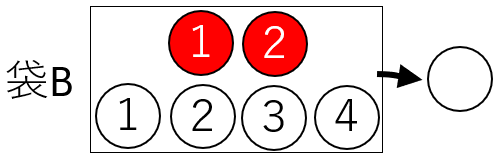
したがって、\(\displaystyle \frac{2}{5}×\frac{4}{6}\)
Step 4:「A・Bの袋から同じ色の玉を取り出す確率」

じゃあ、「両方とも赤」と「両方とも白」って、掛ける?それとも足す?

うーん、今度は……足す?
正解は、「足す」です。
「A・Bの袋から同じ色の玉を取り出す確率」は、「両方とも赤」または「両方とも白」。
このように、両方の事象のうちどちらかが起こればよいときは、確率を足して求めます。
したがって、\(\displaystyle \frac{3}{5}×\frac{2}{6}+\frac{2}{5}×\frac{4}{6}=\frac{7}{15}\)
振り返り

足すのか掛けるのか、ごっちゃになりそう……。

じゃあ、さっきの問題をもう一度振り返って整理してみようか!
求めたいのは「A・Bの袋から同じ色の玉を取り出す確率」でしたね。
この確率は、「両方とも赤を取り出す確率」と「両方とも白を取り出す確率」の2つに分けて考えました。
「A・Bの袋から同じ色の玉を取り出す確率」は、「両方とも赤」を取り出してもいいし、「両方とも白」を取り出してもOKです。
つまり、どちらが起きても大丈夫なときは「足す」です。
一方で、「両方とも赤を取り出す確率」は、「Aの袋から赤玉を取り出す」かつ「Bの袋から赤玉を取り出す」必要があります。
つまり、どちらも起きないといけないときは「掛ける」です。

なるほど!どっちでもいいときは「足す」、どっちものときは「掛ける」か!!

その通り!今、自分が何の確率を求めているのか、「どっちでもいい」なのか「どっちも必要」なのか、そこを見失わないようにしようね!
独立な試行

最後に、確率を掛けるときに注意してほしいことがあるから、説明させてね!

はーい!よろしくお願いします!
2つの確率を掛けるときには、それぞれの試行が独立でなければなりません。
「独立」とは?
試行が独立とは、試行の結果が互いに影響しないことをいいます。
今回の問題では、「Aの袋から玉を取り出す」試行と「Bの袋から玉を取り出す」試行が独立です。
Aの結果がBの結果に影響を与えないので、確率を掛けて求めることができました。
独立でない試行の例
では、独立でないのはどんな場合でしょうか。
たとえば「Aの袋から2個の玉を取り出す」場合を考えてみましょう。
1個目を取り出し、その玉をもとに戻さずに2個目を取り出すと、1個目の結果によって、2個目の状況(残りの玉の色の割合)が変わってしまいます。
つまり、1回目の結果が2回目に影響しているため、この2つの試行は独立ではありません。

このような場合は、確率をそのまま掛けることはできないから注意しようね!
まとめ:確率の加法定理

さて、今回のまとめだよ!
2つの試行S,Tにおいて、一方の試行の結果がもう一方の試行に影響を与えないとき、試行S,Tは独立であるという。
試行Sで事象Aが起こり、試行Tで事象Bが起こるとき、独立である場合には次の関係が成り立つ。
\(P(A\cap B)=P(A)P(B)\)

ありがとうございました!!
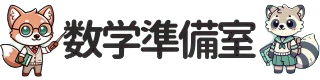
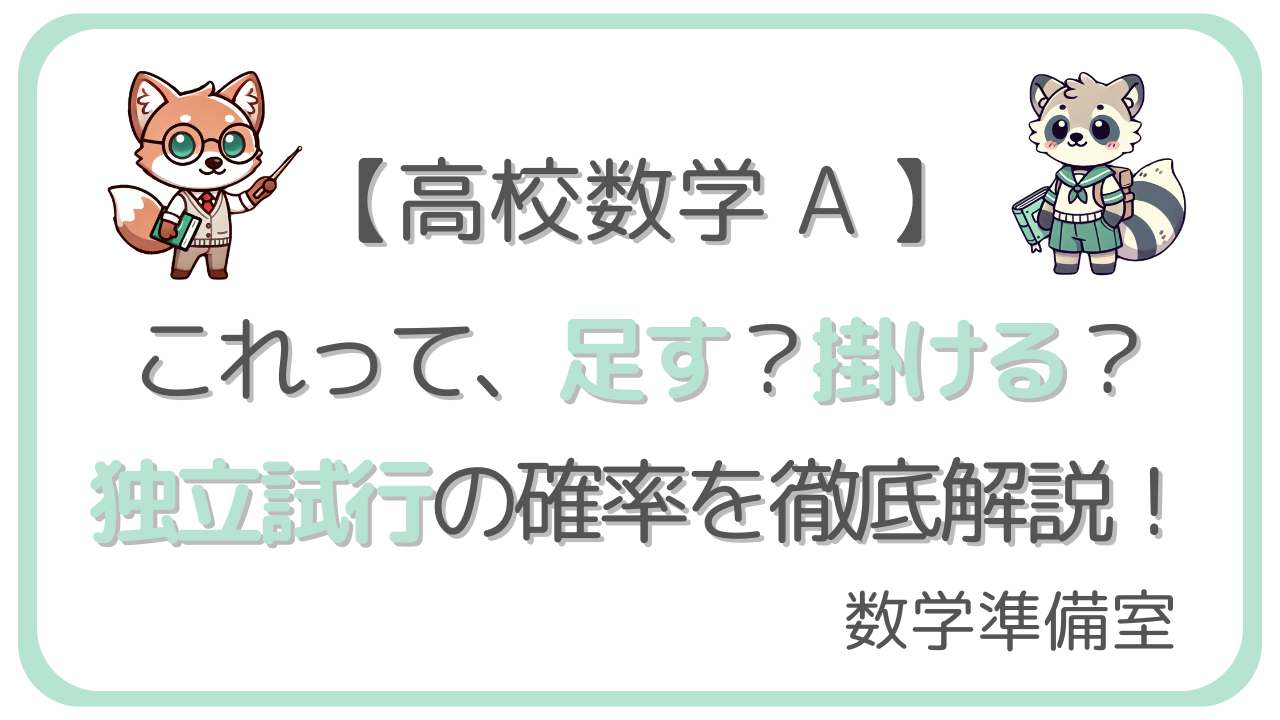
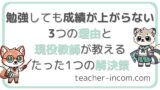
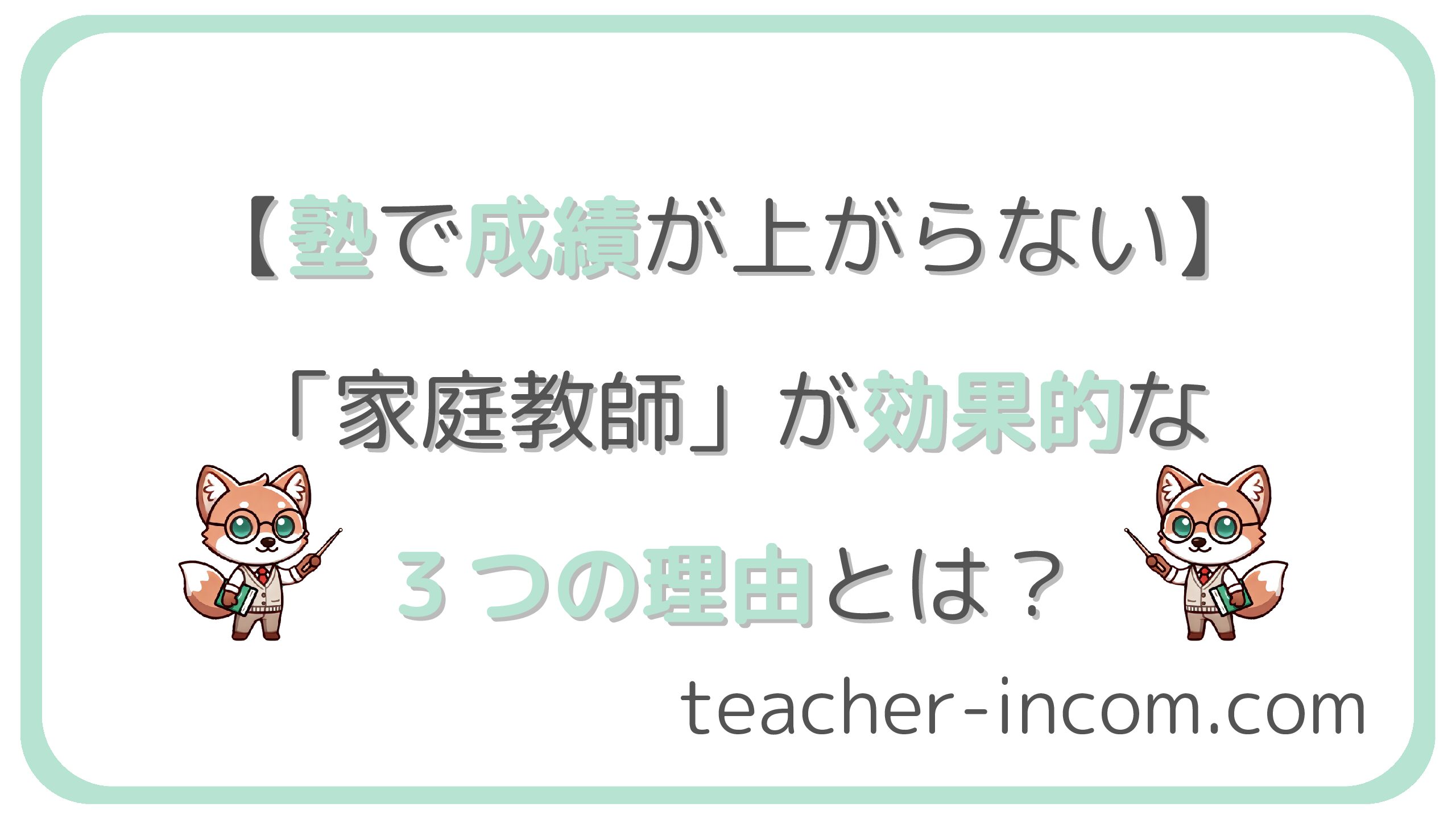
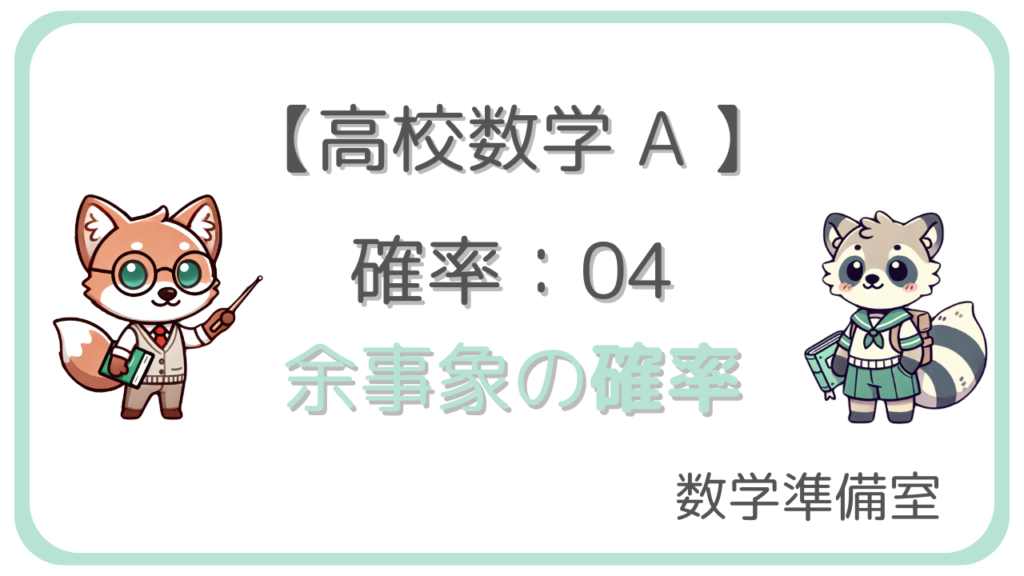
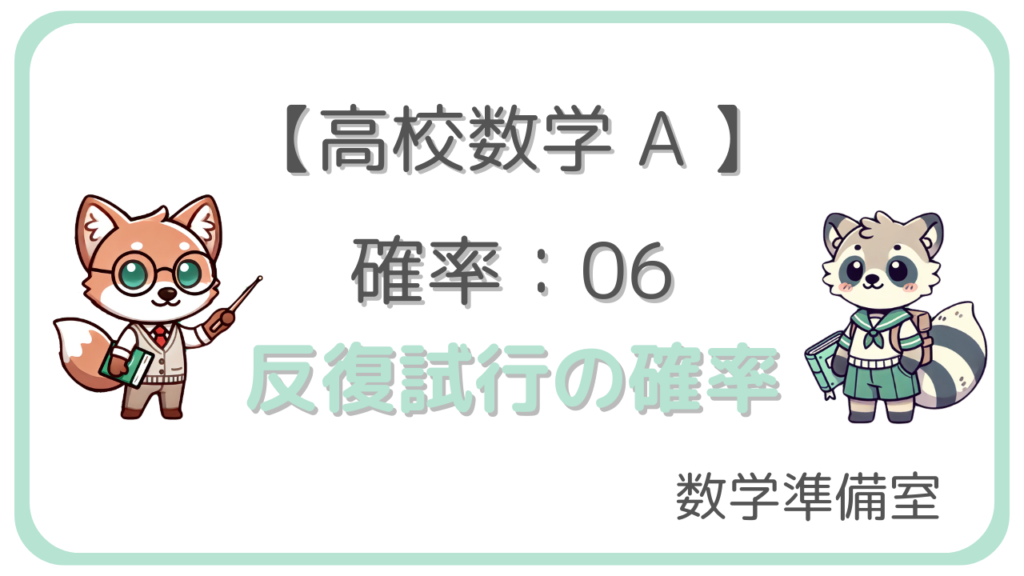
コメント