
今日の板書はこれ!
事象Aが起こったときに事象Bが起こる確率(条件付き確率)を\(P_A(B)\)で表す。
\(n(A)≠0,\:P(A)≠0\)のとき\(\displaystyle P_A(B)=\frac{n(A\cap B)}{n(A)}=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}\)

もっと詳しく願いします!!
現役教員として数学を教えている「さん」と申します。
「人より勉強に時間がかかる」と感じていませんか?
私の学校にも、同じ悩みを抱えて苦しんでる生徒がたくさんいます。
• 「教科書や参考書の内容がわからなくて、読むのに時間がかかる」
• 「解答の意味が理解できず、勉強が進まない」
教科書や参考書の内容を理解するには、「自分なりに噛み砕いて考える力」が必要です。
でも大丈夫!
このサイトでは、私が受けた質問や、つまずきポイントをもとに、わかりやすく解説していきます。
意味から理解し、噛み砕き方をマスターしましょう!!
条件付確率
事象Aが起こったという前提のもとで、事象Bが起こる確率を条件付き確率といい、\(P_A(B)\)で表します。
多くの生徒が、条件付き確率\(P_A(B)\)と\(P(A\cap B)\)を混同しがちです。
ここでは、その違いをわかりやすく解説します。

次の例題で解説するよ!
例題
箱の中に1から7までの青色の番号札7枚と、8から12までの赤色の番号札5枚が入っている。
(1) この箱から番号札を1枚引くとき、その札が青色の偶数である確率を求めよ。
(2) この箱から番号札を1枚引いたとき、その札は青色であった。その札が偶数である確率を求めよ。
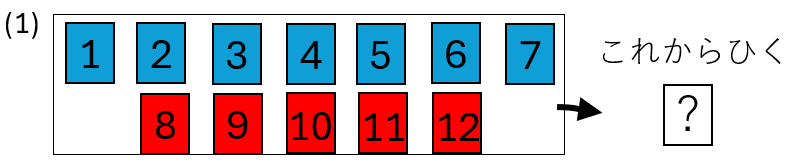
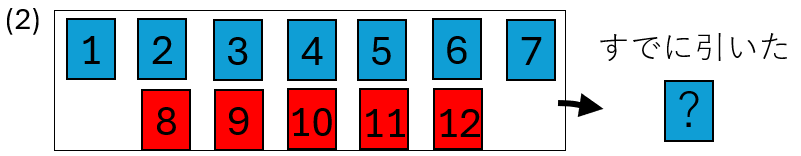
(1) AかつBの確率
箱の中に1から7までの青色の番号札7枚と、8から12までの赤色の番号札5枚が入っている。
(1) この箱から番号札を1枚引くとき、その札が青色の偶数である確率を求めよ。
まず、箱の中の札を整理してみましょう。
- 青色の札:奇数が 4枚(1,3,5,7)、偶数が 3枚(2,4,6)
- 赤色の札:奇数が 2枚(9,11)、偶数が 3枚(8,10,12)
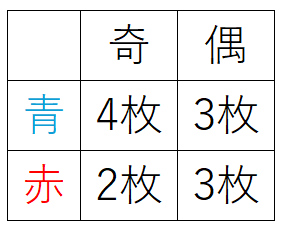
ここで、「青色の札である」という事象をA、「偶数の札である」という事象をBとします。
求めたいのは、「青色かつ偶数の札を引く確率」\(=\color{red}{P(A\cap B)}\)です。
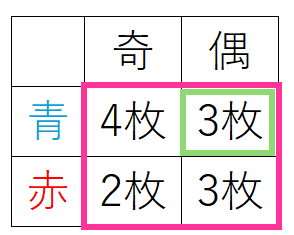
分母(全体)は「12枚の札から1枚を引く」ので 12通り。
分子は「青色かつ偶数を引く」ので 3通り。
したがって、\(\displaystyle\color{red}{ P(A\cap B)}=\frac{\color{green}{3}}{\color{hotpink}{12}}=\frac{1}{4}\)
(2) Aが起きたときBが起こる確率
箱の中に1から7までの青色の番号札7枚と、8から12までの赤色の番号札5枚が入っている。
(2) この箱から番号札を1枚引いたとき、その札は青色であった。その札が偶数である確率を求めよ。
求めたいのは「青色を引いたという条件のもとで、その札が偶数である確率」
つまり、\(\color{red}{ P_A(B)}\)です。
(1) では、「12 枚の中から青色かつ偶数の札を引く確率」すなわち、\(\color{red}{P(A\cap B)}\)を求めました。
一方、(2) では 「青色である」 ことがすでにわかっている 状況です。
条件付き確率は、条件によって全体(分母)が絞られます。
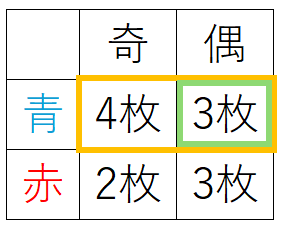
全体(分母)は「青色の札7枚から1枚を引く」ので 7通り。
分子は「青色の札の中で偶数を引く」ので 3通り。
したがって、\(\displaystyle\color{red}{ P_A(B)}=\frac{\color{green}{3}}{\color{gold}{7}}\)

つまり、条件付き確率って、全体の取り方が変わるってこと?

その通り!
条件付き確率では、「条件の中だけ」 を新しい全体として考えるんだ。
(2)を 確率 ÷ 確率 で求める。
箱の中に1から7までの青色の番号札7枚と、8から12までの赤色の番号札5枚が入っている。
(2) この箱から番号札を1枚引いたとき、その札は青色であった。その札が偶数である確率を求めよ。
条件付き確率は \(\displaystyle\frac{\text{確率}}{\text{確率}}\) つまり、\(\displaystyle\color{red}{ P_A(B)}=\frac{\color{green}{P(A\cap B)}}{\color{gold}{P(A)}}\) で求めることができます。
求めたいのは、「青色を引いたという条件のもとで、その札が偶数である確率」。
したがって、\(\displaystyle \color{red}{ P_A(B)}=\frac{\color{green}{\text{青色かつ偶数の札である確率}}}{\color{gold}{\text{青色の札である確率}}}\)を求めます。
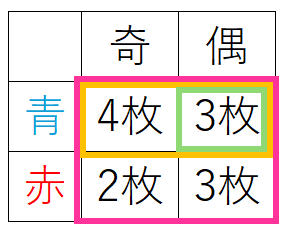
分母「青色の札である確率」は、\(\displaystyle\color{gold}{P(A)}=\frac{\color{gold}{7}}{\color{hotpink}{12}}\)
分子「青色かつ偶数の札である確率」は、\(\displaystyle\color{green}{P(A\cap B)}=\frac{\color{green}{3}}{\color{hotpink}{12}}\)
したがって、\(\displaystyle\color{red}{ P(A\cap B)}=\frac{\color{green}{P(A\cap B)}}{\color{gold}{P(A)}}=\frac{\frac{\color{green}{3}}{\color{hotpink}{12}}}{\frac{\color{gold}{7}}{\color{hotpink}{12}}}=\frac{\color{green}{3}}{\color{gold}{7}}\)

確率÷確率でも求めることができるんだね!

具体的な場合の数がわからないときに使うよ!
まとめ:条件付き確率

さて、今回のまとめだよ!
事象Aが起こったときに事象Bが起こる確率(条件付き確率)を\(P_A(B)\)で表す。
\(n(A)≠0,\:P(A)≠0\)のとき\(\displaystyle P_A(B)=\frac{n(A\cap B)}{n(A)}=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}\)

ありがとうございました!!
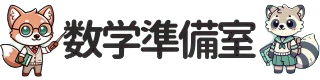
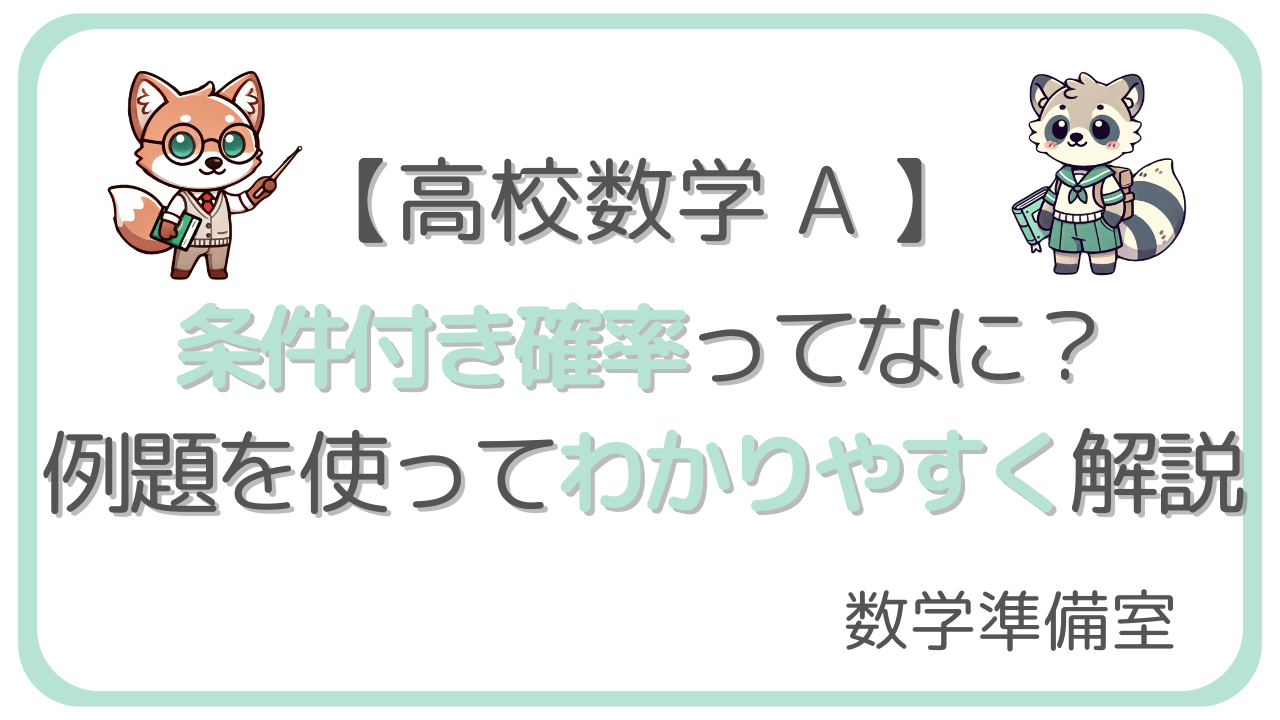
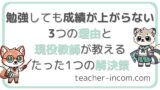
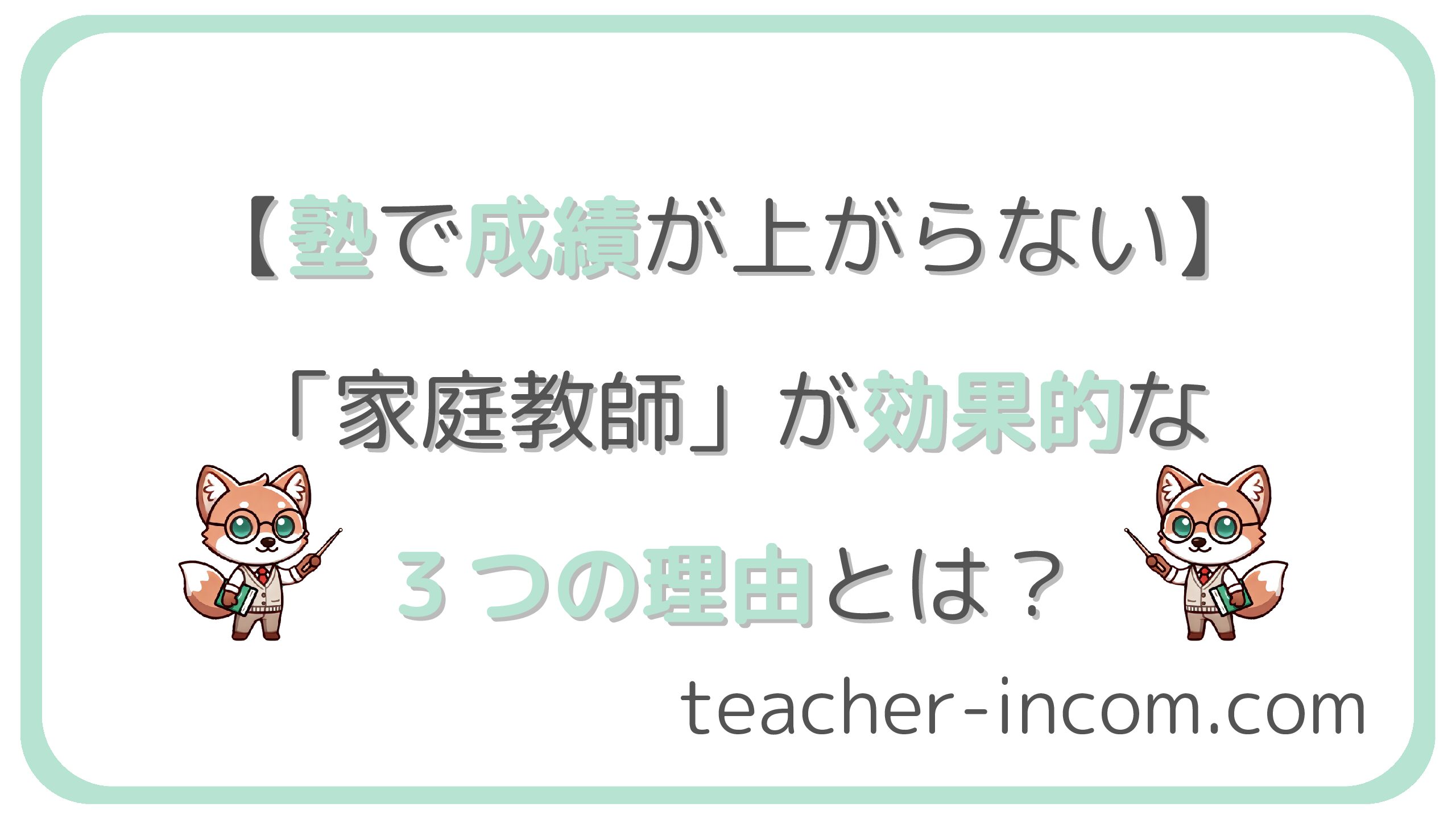
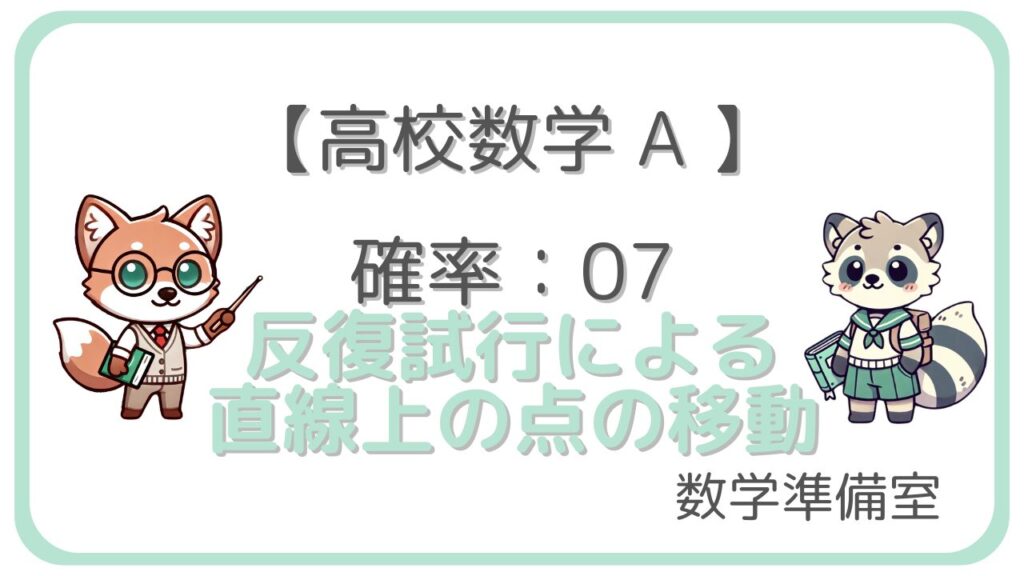
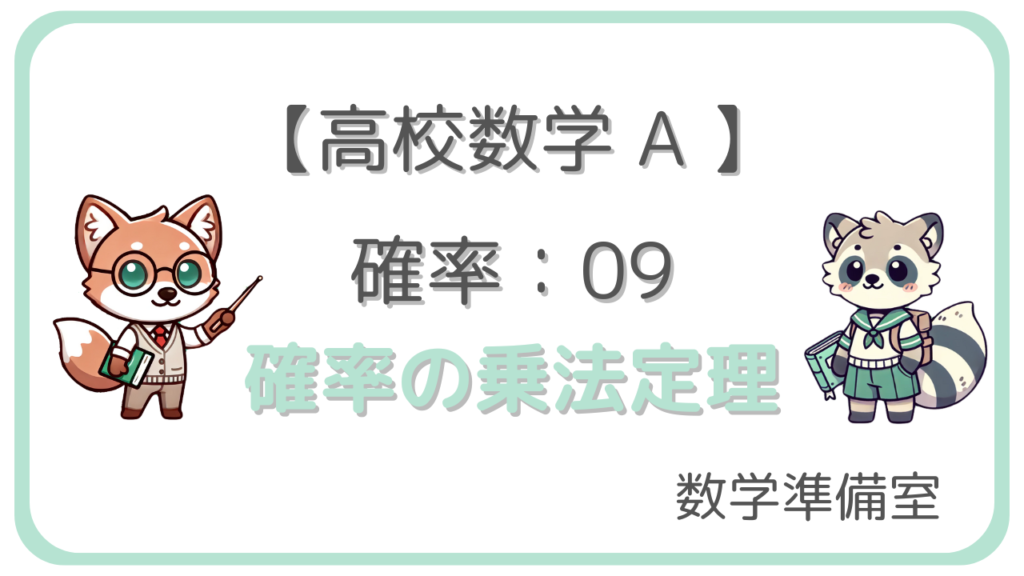
コメント